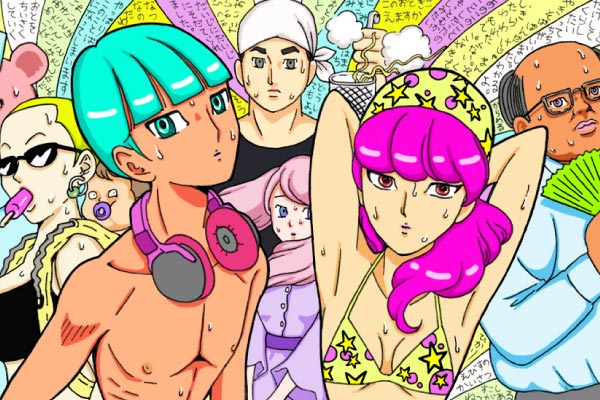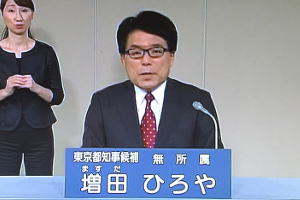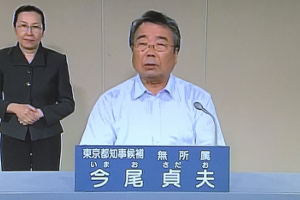「まあ、がんばれや」
祖父から「声」が消えたのは、昨年のことだった。
地元は小さな島の外れ。そこにある実家の居間で対面するやいなや、力強い目線がこちらを向く。しかし、元気なのは目だけで、ペースメーカーで心臓は動くも、口だけが動かず、衰弱しているよう。その光景にこちらの気持ちが動揺し、声を失った。

Photo by Justin Leonard (CC BY 2.0)
セミの声が聴こえる、じわりと汗ばむような夏。それは、東京では国会前など路上で声を上げるような動きが大きく取り上げられる時期だった。ふだんは東京に住んでいるので、実際、そういう行進や声を見聞きした。若者の声がなにかを変えるのかもしれない、人々にそう思われる瞬間もあっただろう。
他方、こちらにあるのは、もうなにも伝えられないのか、口喧嘩もできないのか、というある種の絶望感。いざそうなると、祖父を前にして、失った声を取り戻そうとしている自分がいた。記憶を手繰り寄せていく。最後に言葉を交わしたのはいつだっただろうか……。
「仕事はなにしとるんだかや」
「編集者」
「そうか。本でも作っとるのんか」
「ウェブメディア」
「ウェッブ……?」
「うん」
「おりゃにはわからんけど、まあ、がんばれや」
帰省するたびに同じようなやりとりを何度もした気がする。田舎だからか、祖父に限らず、両親にさえ、仕事のことをほとんどうまく伝えることができない。もちろん伝える義務はないし、知らないことをしているくらいがちょうどよいのかもしれないけれど。

Photo by Dávid Sterbik (CC BY 2.0)
祖父はスマホを知らない
祖父はスマホを知らない。
両親はスマホを使っている。
両親はスマホでYahoo! JAPANとLINEだけ利用している。
実家にはパソコンがない。
ウェブメディアなんて、見たことも、聞いこともない、という(実際は目にしているが、そのことを認識してはいないのだ)。
そういう環境で生まれ育ったぼくが、なぜかメディアで働いている。そして、3年近くメディアの動向を追い続け、メディアについて人より少しだけ詳しくなったぼくは、いまでは海外に取材に行くようなこともある。
ポータルから検索へ、検索からソーシャルへ、そしてその次へ――。メディアに大変化が訪れている。
15世紀、グーテンベルクによる活字印刷の発明が「マス」に届くメディアを生むことになったが、21世紀のいま、「マス」という概念はほぼなくなりつつあるだろう。一方で、ソーシャルメディアやライブ配信などで生まれているコミュニケーションを見ていると、パーソナルな側面に注目が集まっているように感じる。
声を上げる人の、声――。
7月10日の参院選。街中で出くわす選挙カーの上から一方的に響く声に、あなたは興味なく通り過ぎてしまうかもしれない。しかし、目を伏せ音楽を聴きながら通り過ぎようとしたあなたに、候補者が1対1で目を合わせた握手を求めてきた場合、どうだろう。情報との接点という意味において、この例は適当ではないかもしれないが、自分と無関係だと思っている世界が、自分がつながっている世界の延長線上に立ちあらわれることは、少なからずあなたに影響力をもつだろう。
しかし、これは言い換えれば、パーソナルなコミュニケーションであるがゆえの危険もはらんでいる。
「フィルターバブル」という言葉があるように、検索サービスやソーシャルメディアにアルゴリズムが介在することで、人々が見たいものしか見えない構造が生まれている。そこでは、自分がつながっている世界がすべてであると錯覚する。
当然、それには幸せな側面もある。しかしながら、情報や言論が両極端に偏り、互いに相容れないような不幸な状況をたびたびネットで――当然、現実でも――目にする。自分とは対極にある言葉や思いを知った上でなにかを決断するのとそうでないのとでは、結果が大きく異なってくる。こと情報との接点において、その点の理解が重要な意味をもつ。
スマホやソーシャルメディア利用者にとっては当たり前かもしれないが、新聞や雑誌のようなパッケージではなくURL単位になってしまったネットでの情報収集において、よほど強く意識しないことには、こうした問題は解消されることはない。
2020年には世界のネットのトラフィックのうち、8割を動画が占めるという見方もある。VR(仮想現実)がさらに普及すれば、フィルターバブルは実害をもたらすレベルになりそうだ。そんな中でも、ぼくたちは確信をもって周りを見わたし、正反対の声にまで耳を貸すことができると言えるだろうか。
政治は若者と目を合わせられるのか
本来、そうした課題にアプローチできるのが、パッケージで届けられる新聞だったはずだ。新聞社の知り合いは口を揃えて、新聞の強みは「一覧性」や「パッケージ」にあると言っている。
ぼくは日常生活で紙の新聞に触れることはないが、実態はどうなのだろう。「情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」(総務省)や「国民生活時間調査」(NHK放送文化研究所)などを見てみると、若者と新聞の接点がなくなっていることがわかる。「消滅」とも表現できる。
10~20代の新聞購読は10%に満たないし、全年代で見てもその閲覧時間は1日10分程度だ。対照的に、20代のほぼ全員がスマホを保有しているし、全年代のスマホ利用時間は平均で1日70分ほどにもなる。ソーシャルメディアの利用率や利用時間も増えている。
すでにネット選挙も実現したいま、この変化は選挙において可能性と課題のどちらも秘めているだろう。特に、今回は選挙権年齢が18歳以上に引き下げられたはじめての選挙になる。(若者が)政治と向き合う――という言葉がいろいろなところで使われるが、向き合うとかアクションとか、なんだかプレッシャーになりそうだ。自分の暮らしとは遠いことのように感じてしまう人も多いかもしれない。しかし、こう考えてみてはどうだろう。
たとえば、自分が携わるメディアという分野。メディアと聞くと、テレビ・新聞・雑誌・ラジオなどたいそうなものを思い浮かべる人もいる。しかし、その意味は媒体とか媒介といった程度の意味である。
いま着ている服も、行きつけのカフェも、そこで飲むコーヒーも、帰りの電車も、好きな音楽も、もちろんこの「ポリタス」も、それを見るためのスマホも、ぜんぶメディア。そう、ぼくにとってのメディアはそういうものだ。
政治も少し似ている。いかにも大きな話で、自分とは無関係だと思いがちだが、メディアのように、実は身近にあふれている。生活の中で出くわした不便なことや不思議なことが、まさかの「あなたと政治との接点」になりうる。わざわざあれもこれも政治が関係しているのかどうか探すのは面倒だけれど、「身の回りにあふれていてしばしば遭遇してしまう」ものだと理解しておけば、「向き合う」よりは気分が楽ではないだろうか。
とはいえ、メディアについてどんどん深掘りして解説をしたとしても、たとえばぼくの家族にとっては無意味に近いだろう。政治について一方的に語っても、読んでいるあなたは疲れるだろう。
メディア状況の語りなど、しまいにはカタカナばかりで埋め尽くされてしまう。ソーシャルネットワーキングの普及や可処分時間の奪い合い、プラットフォームの優位性、ネイティブ広告、インフォグラフィック、A/Bテスト……大多数にはどうだっていい。
では政治の話はといえば、大仰でわかりづらい漢字の羅列だ。そちらは、どうだっていいとは言い切れないけれど……あ、アベノミクスはカタカナか。カタカナか漢字かは一旦置いておこう。まずは政治の身近さを感じよう。身の回りにない? もしかしたら、日常は、思っているより、自分のことでいっぱいなのかもしれない。けれど――。
投票日が目前にやってきた。スマホに夢中でも、仕事が忙しくても、その日は来る。今回選挙権を持つことになった18歳をはじめ、多くの若者はどうしたらよいのだろうか。
自分の選択に責任を持つことができる日として、思い出に残すのもひとつ。インスタグラムに「投票済証明書」の写真をアップするくらいでもよいだろう。まずは投票所に足を運ぶことで、その現実を感じてほしい。そして、投票結果がどんなものであろうと、その目で、その耳で、しっかり記憶してほしい。
「おりゃにはわからんけど、まあ、がんばれや」
記憶の中の祖父の声。それは、わからないことを応援してくれる声だった。
政治がわからない。投票する意味がわからない。誰がいいのかわからない。そんな状態であっても、背中を押してくれる人たちがいる。自分の意志で、その選択を精一杯悩んでほしい。
終電を逃したぼくに早寝の母から電話
大事なプロジェクトが終わった2月のある日、24時過ぎ。ぼくは池袋駅で終電を逃していた。電車の時間だって、政治に関係することだ……なんて無理やり先ほどの話につなぐことはしない。とにかく、西口でタクシーを待つための長蛇の列に並んでいた。
なにもやることがなく、スマホの画面に目をやると、数時間前に母からの着信が1件入っていた。なにかの異常を知らせたいのだと、すぐに察知した。
小さな島からこちらに出てきて、今年で8年が経つ。3兄弟で唯一、遠くにいるにもかかわらず、実家との連絡は半年に1度くらい。帰省することを知らせる程度だ。そして、田舎に住む母はいつも寝るのが早かった。だからこそ、なんとなく察するものがあったし、いざ電話をかけて、この遅い時間に母が出たことで覚悟を決めた。
母の声が聞こえる前に「じいちゃん……?」とぼくから尋ねた。
「……うん」
母のその声で、翌朝の始発で島へと戻ることにした。
祖父の声を頭の中で再生しながら、帰宅後すぐに準備をした。
帰省するたびに――昨夏の帰省のときもそうだったが――家族に祖父が声を発したかどうか聞いていたことを思い出す。でも、やはり、一度消えた声は二度と聞こえず、呼びかけには目で応えていたらしい。
家に帰ると、地元の人からは祖父に声があったころの話を、家族からは祖父の声が消えた最近の話をそれぞれ聞いた。居間は祖父について語り合う声で充満していて、悲しさは少しずつ嬉しさに変わっていった。最期のとき、病室の窓際にいたという声なき祖父は、なにを思っていたのだろう。もしぼくがそこにいたら、どんな声をかけてくれただろう。
「そうか」「まあ、がんばれや」
きっと、大きく受け止め、優しく突き放してくれたのではないかと、なんとなく思う。

Photo by 佐藤慶一
消えた声の行方
葬儀が終わった翌日、東京に戻る新幹線で――。
実家のタンスの上にあったアルバムの写真をいくつかスマホで撮ったことを思い出す。フォルダを開くと、その1枚に背広を着た祖父が映っていた。十数年前だろうか。テーブルにはビールや日本酒、刺身の盛り合わせ、オードブルなどがあり、祖父は白い歯を見せて笑っている。どうやら祝い事をしている場のようだ。
「必勝」
壁に貼られた3枚の大きな白い紙の真ん中に、墨字でそう書かれている。その熟語の横には、見切れるように祖父の名前。それぞれ「◯◯君」「◯◯殿」「◯◯候補」と3通りある。
そう、祖父は政治家だったのだ。島の小さな自治体の首長ではあるが。
ふつうの農家から行政へと乗り出すという、少し変わった道を進んだ。そんな祖父の背中はいつも大きく見えていた。そして、“選ばれた”経験をもつ祖父こそが、なにかを“選ぶこと”の意味を、どうにかぼくに教えてくれた気がするのだ。

Photo by Yosuke Watanabe (CC BY 2.0)
また、夏が来た。かつて政治家として声を上げていた祖父から、声が消えた季節。
声を上げていた男から、声が消えてしまった――その事実は、いまのぼくにとって、ひどく切実に感じられるものだ。目をつむれば、あの懐かしき「声」が、ありありと聞こえてくる。こんなときに都合良く、説教のように問いかけてくる。
自分で考えろ、疑え、選べ、そして未来をつくれ、と。