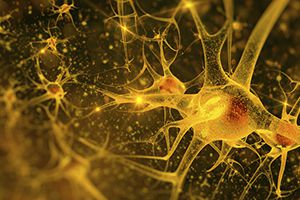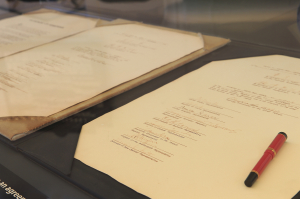私たちの国は曲がりなりにも70年間、主体的には戦争をして来ませんでした。曲がりなりにも――。私たちの国の憲法のたたえている「平和主義」の外に置かれ続けている沖縄の現状を直視すれば、「護憲」を唱えているだけではなく、むしろその実現へ向けてたゆまぬ努力を必要とされていることは理解しています。それでも、すべての戦争は「自衛」の名の下に始められるのだという冷静で大変リアルな認識から、どのような戦争も政治の延長ではなく、政治の放棄であると考えた結果、少なくとも私たちの軍隊が他国で人を殺してはこなかったという重い事実。その70年間の積み重ねによって築いてきた信頼は、恐らく敬意を表するに足る歴史だったと思います。
先の戦争で(この言い方がいつまでも通用して欲しいですが)私の父は3年近くシベリアに抑留され、母は東京大空襲を経験しました。ふたりとも口をそろえて「戦争はもうこりごりだ」と言っていました。その「厭戦」の核にあったのは被害者意識であり、その認識があの戦争の一部でしかないことは中学生になる頃には気付かされました。直接的な被害体験のない私たちの世代は、だからこそ「被害」としてではなくあの戦争を再定義していく必要があるし、むしろその可能性が開かれているのだと前向きに考えてきました。それは今も変わりません。

Photo by 石川光陽
私は1962年に生まれました。今年53歳です。私は今までの人生で、ただの一度も人を殴ったことがありません(夢の中では別です。夢ではもっとずっとひどいことをしてます)。
小学校の入学式のあと、それぞれの教室に入った時のことです。並べられた机のうしろ、ロッカーの前で篠田君と樋口君が喧嘩をしていました。正確に言うと、篠田君が樋口君をいじめていました。まだ名前も知らなかったそのふたりの間に入り、私は「やめろよ」と言いました。その直後、私は篠田君に顔中をひっかかれ、保健室送りになりました。その時の傷は、今も私の目元に残っています。

Photo by PIXTA
その傷の代償としてかどうかは定かではありませんが、私は学級委員に選ばれました。以後、6年間ずっと学級委員です。こうなるともう、主体的に喧嘩をすることなど、担任の先生もクラスメイトも許してくれる雰囲気はありませんでした。ですから、僕の中の極端な厭戦気質は、周囲の期待によるものであり、自らが望んだものでは必ずしもありませんでしたし、父母から意識的に受け継いだつもりもありません。もちろん腹は立ちますし、殴りたいと思うことはあります。しかし、結果として、その後の人生で負の感情の発露としての暴力を、少なくとも直接的な暴力を選択肢には入れてきませんでした。できなかったのです。
だから、これは、自慢でも何でもありません。むしろコンプレックスだった時期もありました。現に、中学時代の友人から「男じゃねえなぁ」と蔑まされたこともありました。でも、53年経ってみて思うのは、まぁ、そんな人生もあるのかなぁと、いうことです。悪くない、と。ひとつの選択肢を禁じ手にしてみることは不自由さ以上に工夫を生む原動力になりました。その工夫は仕事にも活かされていると自負しています。どうせ今やっても全く喧嘩慣れしてませんから、勝てっこないですし。残りの人生もできることなら人を殴らずに過ごせたらいいなぁとそんなふうに考えています。

Photo by Matthias Ripp(CC BY 2.0)
個人史を国の歴史と重ねることの危険性を承知した上であえて言えば、自ら選んだ価値観では必ずしもない「厭戦」という意識とともに歩んで来たという意味において、今までの日本は私の大先輩であります。日本という国が軍備にあてる費用と意識を別の方面に向けることに成功したこの70年の歴史は、やはり、全てとは言わないまでも誇り得るものだと思います。
狡猾さと隣り合わせのその知恵と工夫は、本来の意味での憲法の平和主義の具現化とは違ったやり方だったかもしれませんが、充分に成熟した大人の振る舞いであったでしょうし、私たちの世代はその恩恵をたっぷりと受けて育つことができました。「国防」における「軍備」の割合をどうするかは、必要な電力における原発の割り合いをどうするかと同様、国民の総意として選択するべき課題でしょう。どのような選択もリスクは伴うでしょうから、あとは情報を開示し合ってみなで決める。ただし、可能な限りリスクは応分に負うというくらいの平等意識は必要だと思います。
ただ、せっかく70年、大げさに言えば「人類史の実験」を曲がりなりにも続けて来ているのですから、何も今さら、どこにでもあるような「一人前」の「男らしい」国家の仲間入りを目指さなくても良いのではないでしょうか。どうしても「一人前」に勇ましくなりたいのなら、やはりきちんとルールブックを自らの手で書き直すべきです。そうせずに振る舞いだけ「一人前」ぶっても、それは決して「男前」ではないでしょう。むしろ卑怯です。どうせ喧嘩しても勝てませんよ。その分の体力と知力と財力を別の方面に今まで通り活かしたほうがいいんじゃないですか。そのほうが今から100年、1000年経った時に、今の日本のあり方がひとつの可能性として語り継がれるのではないかと、そんなふうに私は考えています。

Photo by Richie Rich(CC BY 2.0)
私たちは、私たちの国は、過去を全否定し、責任者を自らの手で粛正し、刷新して新たな時代を生きる――そんな歴史の重ね方はしてこなかった。戦前との継続性の上に戦後を築いてしまった。それはアメリカが望んだことでもあったでしょうし、私たちの国民性に合致した選択だったようにも思うのです。そのことの功罪を少なくともきちんと認識する必要が、私たちにはあるでしょう。
先の戦争による加害についての謝罪を、もし、終わりにしたいのなら、私たちはやはり70年前に遡って、自らの手で自らの継続性に終止符を打つべきだと考えています。もし、そんなことができるのなら、是非そうするべきだと思います。もちろんそれは、政治家だけの罪を問うことを意味しません。私の父や母を含めた話です。もしそれが不可能であるなら、別の形を模索すべきです。
「謝罪」は、特定の日に、その時々の政治家の言葉によって示されたり示されなかったりするべきものではありません。私たち一人ひとりの国のあり方に対する一つひとつの判断。それが具体的に更新され、体現されていく日々の積み重ねによって、365日示され続けていくような類のものでしょう。それこそが私たちの持つべき「談話」であり、それこそが他者との「対話」を未来に実現する萌芽に他なりません。
この国が、これからも私の良き先輩であり続けることを願っています。