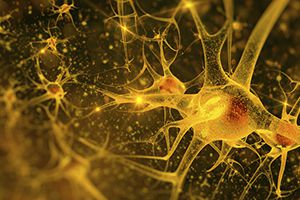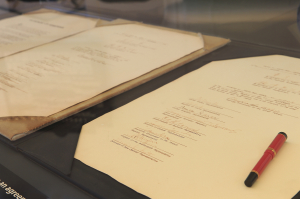原稿を依頼されたとき、戦後70周年に際して「あなたが国民と世界に向けてスピーチをするとしたら」というこの仮定法に、一瞬ひるみました。
スピーチは書けるだろうし、戦争と敗戦と占領期、主権回復から高度経済成長期にわたる歴史的過程についていろいろ考えることも感じることもあるけれど、さらに「国民と世界に向けて」を同時に日本語で書くことは、僕にとって至難の業です。
第一、ここで言っている「国民」とは、単なる「この国の市民」や「日本語話者」ではなく「国籍も人種的自己認識も、日本人」というタイトな限定が入るので、とうぜん、長く日本にいながらそれらとは別の立ち位置で物を言う(あるいは言うことを期待される)存在としてある僕が、「国民に向けて」何かを自然に言うことはない。自然に、が悪ければ「素直に」としましょう。
国民とか、我が国とか、いまもキーを打ちながら生成させているこの日本語が「国語」と呼ばれる、ということを考えると、あ、そういうパッケージでまとめられたんだな、と歴史の浅瀬に足を留め、周りをきょろきょろするばかりです。
むかし、ヴィム・ヴェンダーズの『ベルリン・天使の詩』という映画を見たことがあります。主人公の天使が吹き抜けになっているベルリンの市立図書館の2階部分に腰を掛け、うつむいて本を読んでいる閲覧者たちを遠目から静かに見渡しています。
僕は天使ではありませんが、政治家が国会中継で「国民の皆様」を連呼しているのを聞くと、まるであの天使のように少し斜め後ろ辺りからそのシーンを眺めている気分になります。そしてその気分の延長で「国民に向けて」何かを言おうとすると、そうではない人々が誰で、彼らは今どこで何をしているのかな、などとつい考えます。余計なことと思われるかもしれませんが、日本語が届く範囲の「国民」ではない人々を心の中で探し出すのです。彼らが見えないと、少しだけ背を向けている感じになる、と言えばいいのかな。政治家が「絆」とか「家族」とか言っているときも、たいがい反射的に、その「絆」と「家族」の縁(へり)の先に腰を掛けて見ているだろう人々の姿を思い浮かべたりします。
「国民」のすぐ後に「世界」と続くからいけないのかもしれません。日本語で「世界」というと、「国民」と比べてどこを指しているのかよく分からないほど茫漠としており、メッセージを向ける相手として不足はないけれど、でっかい合切袋にいろいろな「世界基準」を詰めて泰然と構えているような大人物を想像します。しかし実際、世界に向けられた日本語のメッセージがいったん翻訳され広がっていくと、日本語の中では想像がつかないような誤解や誤認が生じることがあります。そうなると、日本語の微妙なニュアンスをたよって自分の判断の基軸をぼかしてみせたり、意味の強弱を操作することはできません。
先日発表された安倍総理の戦後70年談話でも、誤解が生まれたのかもしれません。政府が用意した英語訳によって、理解への「失われた機会」がいくつかあったように思います。その一例を挙げてみましょう。
「日本は、世界の大勢を見失っていきました」
In this way, Japan lost sight of the overall trends in the world.
第一次大戦後、欧米諸国が植民地支配から脱却し新たな国際秩序へと舵を切ろうとする過程の中で、当初、日本も「足並みを揃え」ようとしたが、世界恐慌が起きると欧米主導の経済ブロック化によって日本経済は逼迫し、力の行使によって解決を試みた、と述べた上で、その行使を止められなかった政治システムの脆さを指摘しています。上の引用は、この言葉を受けている部分です。
逐語訳として過不及はないが、「世界の大勢」を trends in the world に置き換えているために「日本」に対置された「世界」に含意される途轍もない力や必然性は伝わらず、「大勢」の訳語である trends も、まるでデイトレーダーが株の値動きを追っているような小さなイメージが重なってしまい、軽い。これでは国家が見るべき羅針盤を無視してあらぬ方向へ突き進んでしまったという重厚なニュアンスが伝わらず、日本が、上手く波に乗れなかったのだという浅く平坦な歴史認識に見えてしまう。
翻訳が上手い下手以前に、たとえば言語が異なるかつて戦った者同士が戦争を語ろうという際に、言葉そのものが背負う風景が違うのは仕方がありません。このことについて、我々は敏感にならなければいけないと思います。
総理談話を受けて書かれた『ウォール・ストリート・ジャーナル』(英語電子版、2015年8月14日)は、談話に5つの要点があるとして、「日本兵も英雄であった」("Japanese Soldiers Were Also Heroes")をその1つに挙げています。総理は、戦後の日本の繁栄について「600万人以上もの帰還者(repatriates)がアジア太平洋の各地から何とか無事に帰れ、戦後日本の復興の原動力となった」と言っています(筆者による、英語版の訳)。原文ではこう書かれています。
戦後、600万人を超える引き揚げ者が、アジア太平洋の各地から無事帰還でき、日本再建の原動力となった事実を
引き揚げ者でも帰還者でも、日本語で読めばそれは軍人にかぎらず軍属も民間人も、つまり老若男女が幾年も掛けて戦地と旧植民地から日本の港へと帰ってきたというあの壮絶な映像や記録に対する記憶が甦り、「日本兵も英雄」というストーリーは描けません。そうしたニュアンスによる問題はほかにも何点か見られますが、要は、日本語で日本人に向けて話しているつもりで戦争のことを外国に向けて語ると、結果として誤解が生じ、「外国人には伝わらない」「分かってもらえない」ということにもなって、対話の手前で話が閉鎖されてしまうことが多いのです。もちろん、英語で語られ日本語に変換されるメッセージでも、同じことが起こりうるわけなのですが。
しかしそもそも、背を向けること自体は、そんなに悪いことだろうか? という問いも立てられると思います。僕自身、いつも真っ直ぐばかり向いているわけでもありません。

『選挙のビラ貼り』S21・4 - 木村伊兵衛
そう思い出させてくれる、1946年4月に写真家の木村伊兵衛が銀座で撮った1枚のモノクロ写真があります。木村は、銀座4丁目北西角の舗道に立ち、銀座通りの向こう、前年春の大空襲で焼き払われた三越百貨店の壁までをレンズに収めています。前景には、地下鉄の出入口で男が立ち会い演説会のポスターを貼ろうとしている姿。道の向こう、板を打ち付けられた三越の飾り窓には、選挙広告がところ狭しと貼られ、窓枠ごとに政党の宣伝や「総選挙教室」といった大きな看板が振り分けられているのを、往来の人々が見上げています。つまりはこの写真が、同年4月10日に行われた戦後初の選挙、第22回衆議院議員総選挙の直前に撮られたことが分かるのです。何と面白い。
でも本当はもっと面白いことがあります。この1枚の写真に、木村が背中を向けてあえて収めようとしなかった現実のことです。彼の真後ろには、銀座随一の名所、かつての服部時計店(現在の和光)、当時は日本を占領下におく米国第8軍駐屯地売店(PX)がそびえていました。カメラを少しだけ左に振れば、もう一軒のPXが建ち(松屋百貨店)、右に振れば交叉点の真ん中で交通整理をする米軍憲兵(MP)が立っていたはずです。4万5000人もいる在京進駐軍が「タイムズ・スクエア」と呼ぶほど、彼らの日常の中心地点だったにもかかわらず、この写真に1人も現れず、しかし彼らと彼らが求める豊かな物資は木村の背中の後ろで静かに息づいているのです。これは木村があえて背いた、あまりにも大きな現実です。
69年前の春の一瞬。ですが、木村伊兵衛のカメラには「今」の先を流れる「これから」を捉えることのできるレンズがあり、しかしそこにはただ無理解ゆえに現実を否定しようなどという姿はありませんでした。だから今を生きる政治家も、報道メディアも、僕らも、丈夫で軽やかなレンズをもって、「言葉を向け合える世界」を撮らなければなりません。