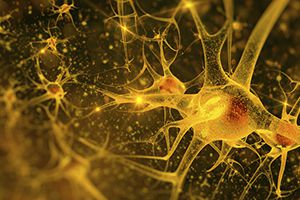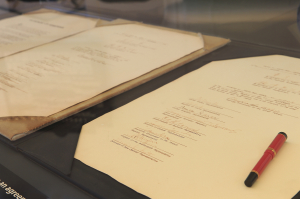アジア太平洋戦争から70年を迎える今年、私たちが生きてきた「戦後」と呼ばれる時代について、かつてない論議が起きています。南方での凄惨な玉砕、島民に多大な犠牲を強いた沖縄戦、そしてヒロシマ、ナガサキへの2度の核攻撃を経て終戦を迎えた同じこの夏には、かつての戦争について改めて振り返り、その実相の解明と、歴史的な省察を促す企画が目白押しです。いまある日本の社会が、その過酷すぎる礎のもとに築かれてきたことを思えば、当然のことと言えるでしょう。
それにしても、なぜ「70年」なのでしょうか。まるで「戦後100年」を迎えたかのような騒ぎではありませんか。あるいはなぜ「戦後50年」に、このような気運が盛り上がらなかったのでしょうか――私には、そのことが、ずっと不思議でした。
むろん、集団的自衛権の行使を可能とする新安保法案への世論の高まり、沖縄の辺野古への基地移転をめぐる国と県との攻防、1964年の東京五輪に続く2020年の新東京五輪をめぐる迷走など、「戦後」について、今年に入り、近年稀なほど、深く問い直すべき諸問題を抱えることになったのが拍車を掛けているのは、言うまでもないでしょう。
けれども、より本質的には、戦後70年という年に、日本がこのような大きな岐路に立たされたことの背景には、次のことがあるように思えるのです。
70年という時の経過は、程度の差こそあれ、私たちに与えられた生涯の時間に、ほぼ一致します。たとえば、敗戦を迎えた1945年にこの世に生を受けた赤ん坊は70歳となり、その人がなしとげてきた生の総体が総括される晩年を迎えています。これにならえば、戦後70年とは、戦後という区切りが、いよいよ、その終盤を迎えようとしていることを意味します。これは、なにも比喩ばかりではありません。
戦後について考えるには、たとえば戦後100年と言われるとき、人に天与された時のスケールとしてはいささか大きすぎます。しかし、80年であっては遅すぎ、60年では早すぎる。戦争をじかに体験している者と、戦争について知らずに育った者と、戦争とはまったく無縁に生まれた者――彼らが共通の卓上で意見を交わすには、戦後70年というのは絶妙なタイミングであり、なおかつ最後のチャンスなのです。

Photo by L'oeil étranger(CC BY 2.0)
そんな希有な年であるにもかかわらず、日本は、いま、かつてない危機のもとに置かれています。4年前の2011年3月11日に起きた大震災の余波と後遺症から、なお抜け出せずにいるからです。とりわけ、東京電力福島第一原子力発電所で起きた3基の原子炉のメルトダウンと、広範囲にわたり拡散した放射性物質から古里を追われた人たちの行く末には、依然、はっきりとした展望が見つかっていません。

つまり、私たちはいま、新東京五輪という新たな飛躍への希望と、未曾有の復興への途上という重い課題が交錯する時代に生きているのです。ところが、新五輪が復興の象徴として語られる一方で、建設費や資材の高騰、そのための人員の不足、そして、東北の復興などどこ吹く風の、反面的な祝祭的高揚によって、新五輪は東北の復興を後押しするどころか、実質的に遅延させ、その現状を忘却の淵にさえ追いやりつつあります。
2兆円を超えるとも言われる新五輪のための国家予算があるなら、なぜ、これを東北の復興に注ぎ込まないのでしょうか。もとより私は、新五輪の誘致・開催そのものに反対の立場でした。案の定、すでに新国立競技場をめぐる悲喜劇だけでも、とんでもない額の公金が消えています。東北の復興を考えれば、どぶに捨てるような愚策です。しかし不幸中の幸いというか、首都の中心には、旧国立競技場の取り壊しによって、広大な空き地が生まれました。

Photo by PIXTA
どうせ新東京五輪を開くのであれば、メイン・スタジアムの新設は既成の施設を使うことで断念し、かの神宮の地には、津波被害や原発事故で古里の家や土地を失った、20万人にもおよぶ人々のために復興の特別区をもうけてはどうでしょうか。そのことで、なによりもまず、被災者の方々の居住と生活を安定させ、五輪にまつわる仕事への就労機会を優先的に受けることができる、抜本的な東北の再生計画に充てるのです。いまなお過酷な現実のもとにあり、未来など見ようにも見ることができない人たちが、新東京五輪の華やかな様子を、首都から遠く離れた仮設住宅のなかで、テレビを通じて視聴することが、どうして復興などと言えるのか。私にはまったく解せません。本当にそれが、戦後70年という、先の例にならえば人の一生にもなぞらえうる記念すべき年に、日本のさらなる未来のために、私たちが共有すべきヴィジョンなのでしょうか?

Photo by Jean-Pierre Dalbéra(CC BY 2.0)
国難の渦中と呼ぶべきこの時期に、新東京五輪などというものがありうるとしたら、それは、あの大震災の被災者たちが、傍観者などではなく、本当の主役となって築き上げるべきものです。そのためにも私は、新国立競技場は建設せず、更地となった神宮の一等地には、震災の避難者20万人のための、新たな五輪と真の復興を束ねて進めるための、一大拠点を作ることを提案します。そして、新しい未来のための国家プロジェクトが、ほかの誰でもない、未曾有の震災の被災者たちの手で築かれるという、かつてない五輪開催の姿を、世界中から日本を訪ねる人々や、それを視聴する地球の津々浦々の市民たちに、わが国が真に誇るべき姿として届けることができたらと、切望します。