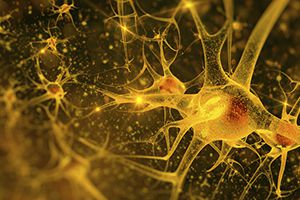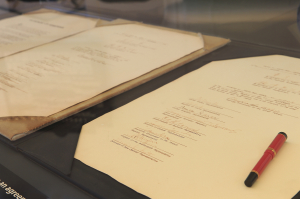私が物心ついたころ、戦争が終わってもう10年以上が過ぎていた。
それでも町はまだ貧しく、路上で眠っている人たちも珍しくなかった。寒い朝など、もつれた髪の老人の身体に霜が降り、そのままどこかへ運ばれていく光景も見た。そうした人びとを横目に、町は少しずつ復興しようとしていた。
幼かった私にとって、戦争とは、街角に立つ傷痍軍人たちの姿だった。傷痍軍人とは、戦場で重い傷を負い、働くことのできない身体になって日本に戻ってきた元兵隊たちだ。

Photo by PIXTA
彼らのうち、ある者は白い着物のようなものを着、白い帽子を目深に被り、義手でアコーディオンを巧みに操り、軍歌を弾いて、喜捨を求めた。脚までも失った人たちも少なくなかった。そうして路傍に立って楽器を鳴らす者もいれば、電車内の狭い通路を進みながら演奏する者もいた。人びとは彼らがそばに来ると、後ろめたげに目を背け、道を除けた。
傷痍軍人たちは、口を固く結んだまま無表情だった。その全身からやり場のない怒りが氷の刃となって放たれているようだった。母のエプロンに隠れている私にも、怒りの刃は突き刺さってくるようだった。それが怖かった。
当時、近所の子どもたちと誘い合って幼稚園に通っていた。
そのなかに、青い目で金髪の、まるで天使のような男の子がいた。普通の日本の名前だったけれど、彼の家は、当時にしては珍しい白いペンキの塗られた瀟洒な家で、庭には緑の芝生が敷き詰められていた。風が吹くと窓のレースのカーテンが揺れて、まるで絵本のようだった。彼は高価なアメリカ製のおもちゃを沢山もっていて、私は彼の家によく遊びに行った。
彼は気前よくいろんなものを見せてくれた。仲良しだった。
でも、たいてい、彼の家には誰もいなかった。そして彼はいつも庭から歩道へおりる石段に座って、誰かを待っているみたいに脚をぶらぶらさせていた。ほんのときどき、赤い口紅を塗った小柄な母親の姿が見えた。大人たちは目配せして何かささやき交わし、子どもたちははやし立てながら石をぶつけた。だから彼はいつも小さな肩を怒らせるようにして、周囲を睨みつけていた。

Photo by simpleinsomnia(CC BY 2.0)
小学校に入ってまもなく、私はその町から引っ越した。以来、彼の消息は知らない。
やがて1964年の東京オリンピックが来て、町から戦争の痕跡はぬぐい去られていった。
そして、私が高校に入ったころ、新聞を読んでいた母が小さな記事に気づいた。あの町で、暴走族のグループがバイクで道路を爆走し、転倒した数人の少年が死んだ、という記事だった。その1人の名前があの男の子と同じだった。もしそれが本当に彼だったとしたら、彼は幼いころと同じ睨むような眼で、最期の闇のなかへ疾走していったのだろうか。
私が生まれる前、私の叔父は戦争に行った。戦後も、「戦うべき時には戦わなくちゃならないんだ」などと声高に語る叔父だった。でも小っちゃいときから弱虫だったんだよ、と親族たちは笑っていた。だから大学生だった彼のところにまで徴兵の通知が来たとき、祖母は心配で半狂乱になり、懸命に縁故を辿り、祖父が遺した田畑を売って、危険な前線に行く可能性の少ない部隊に配属してもらおうと必死だったのだそうだ。
あるとき、大陸にいた叔父の部隊は、前線から遠く離れた(と考えられていた)地を行軍していた。するとそこへ突然敵が現れ、銃撃戦が始まった。叔父は、びっくりして、腰を抜かして、逃げることもできずにその場にへたり込んでしまった。すると叔父の目の前に、さっきまで談笑しながら行軍していた戦友の頭が、ぽとんと落ちてきたのだそうだ。
「ついその前まで、一緒にしゃべってたんだよ。笑っていたんだよ。でも、突然すごい音がして、そして、頭だけになっちゃったんだよ。なあ、わかるかい? さっきまでしゃべってたんだよ。あいつは一番の友だちだったんだよ」
叔父はふとした瞬間に記憶がフラッシュバックするらしく、その話を繰り返し姪である幼い私に語った。
戦地で終戦を迎えた叔父は捕虜となり、極寒のシベリアに数年抑留された。日本に帰ってきたときはやせ細り、重度の肺病で、会社勤めは無理な身体になっていた。それでも土地の名家の坊ちゃんなので、お酒を飲んでは軍歌を歌い、気炎を上げる。そしてときどき、「降ってきた戦友」の話と、シベリアの収容所にいた気のいいロシア人たちの話をつぶやく。
「おれはなぜだか生きているけどな……」
平和こそが正義だ。平和こそが力だ。私はそう思う。それだけが私の言いたいことだ。