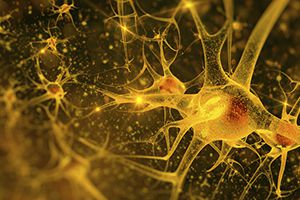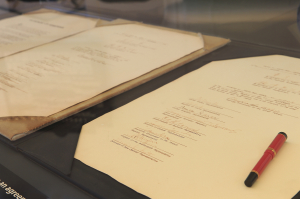お盆月の8月のある夜、大蓮寺の墓地で詩を読む会が催された。詩人・上田假奈代と続けている「詩の学校」の特別編で、受講生は本堂で回向をした後、真っ暗な墓碑群の中に分け入り、月明かりの下、銘々に詩を編んだのである。
いつもは小一時間もしたら、一つ所に集まって、自作の朗読会となるのだが、そう指示されたわけでもないのに、誰もが決まって死者への想いを言葉に綴る。亡くなった身近な人へ、あるいは災害や事故死した誰かへ、有名無名にかかわらず、夜の死者に鎮魂の詩を贈る。
かつて日本の伝統的なコミュニティには、生者と死者が共生していた。生きている者だけがすべてに優先するのではなく、ここにはいない死者からの承認や了解を必要とした。宗教の数々の儀礼はそのために開発されてきたともいえるのだが、別の言い方をすれば、生者の横暴を抑止するために、そうやって死者の声を聞き取ろうとしたのではなかったのか。
戦後70年、生者の権利ばかりが主張され、死者の存在は近代のシステムに封印された。若さや健康が崇拝され、死に至るプロセスとしての老いや病は医療・福祉の対象として回収されていく。戦後社会とは、死を忌避して、生の絶対肯定に勤しんできた、もうひとつの格差社会でもあったのだ。
しかし、すでに、生者の優位にも翳りが見える。出生者を死亡者が遥かに上回る多死社会では、死は病院から家庭・地域へと帰還する。戦後間もなくまでそうであったように、死は日常の光景として蘇るのである。また単身社会にあっては、一人一人の死を誰が看取り、誰が弔うのか、地域社会の新たな役割が問われてくる。死はひとりでは完結しないのである。
伝統的なコミュニティをそのまま再生することは難しい。であれば、われわれはどのように死者の声を聞き届ければよいのか。生者の論理としての現代的な規範とか秩序から距離を置き、あえて無為な世界に引きこもることも必要だろう。墓場の詩作がそうであったように、暗闇の中に溶け込みながら、自己の感覚を溶解させることも大切なのかもしれない。そうして、死者を受信する身体をつくるのである。
終戦とお盆が重なる8月は、死者が訪れる季節である。明けて9月、死者に参る彼岸の今、またその囁きに、しばし耳をそば立ててみたい。

Photo by Toshimasa Ishibashi(CC BY 2.0)