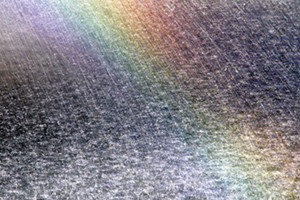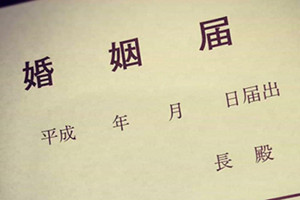今回2019年7月の参議院選挙では、候補者の女性比率が28.1%と過去最高であった。まだ3分の1に満たない数字だが、少なくとも改善の方向にあるのは評価したい。
過去の参議院選挙の候補者を見てみると、1980年における女性比率は わずか6.3%だったが、拘束名簿式比例代表制を導入した1983年で12.8%に上昇、以降は順調に伸びていって、2001年には 27.6%と最高の比率となった。
しかしその後に伸び悩みがあり、前回の2016年 は24.7%となっている。つまり今回の28.1%は、18年ぶりの記録更新となるのだ。
ただしその内実は各政党により大きく異なる。主要政党における候補者の女性比率と、非改選の議員も含めた、選挙前の参議院での各会派の女性比率を見てみよう。
自民 :14.6%(82人中12人) 選挙前15.2%
公明 : 8.3%(24人中 2人) 選挙前20.0%立憲 :45.2%(42人中19人) 選挙前25.0%
国民 :35.7%(28人中10人) 選挙前25.9%
共産 :55.0%(40人中22人) 選挙前35.7%
維新 :31.8%(22人中 7人) 選挙前26.7%
ここから少なくとも二つが読み取れる。一つ目は、与党と野党で大きく違いがあるということ。二つ目は、与党は選挙前より候補者の方が、女性比率が低くなっていることだ。
前者について気になるのは、与党の方が選挙には強いため、候補者の女性比率の少なさが結果として当選者の女性比率を下げる要因となりうる点だ。前回の参議院選挙においても、全ての候補者における女性比率が24.7%だったのに対し、当選者における女性の比率は23.1%と低くなる結果となった。
与党は選挙前より候補者の方が、女性比率が低くなっている
後者についてはいうまでもないだろう。自民党と公明党の両党はたとえ女性候補が全員当選したとしても、選挙前と比べて女性比率は確実に下がることになる。「女性活躍」とやらの正体みたり、という気分になるひどい話だが、その議論に入る前に、国際的に見た日本での女性の地位と、日本政府の取り組みについてご紹介したい。
国際的な女性の地位を示す数字として、「ジェンダーギャップ指数」がある。この指数は、経済、教育、健康、政治の4つの分野のデータから作成され、0が完全不平等、1が完全平等を意味している。最新である2018年の日本の総合スコアは0.662、順位は149カ国中110位と全くお寒いとしかいいようがない状況であり、その原因は政治分野と経済分野のギャップの大きさにあるとの議論は広く知られているところだ。
この状況を日本政府も良しとしている訳ではない。政府は「男女共同参画社会」の実現を目指し、さまざまな施策をとっているのだ。政治分野については、昨年5月23日には「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」が国会で成立している。
この法律は、衆議院、参議院及び地方議会の選挙において、男女の候補者の数をできる限り均等とすることを目指すことなどを基本原則とし、政党や政治団体にも努力するよう課したのが特徴だ。罰則はないが、しかしれっきとした法律である。
自民党と公明党には、「努力」した形跡は全く見られない
ひるがえって今回、選挙前よりも候補者の女性比率の方が低い自民党と公明党には、「努力」した形跡は全く見られないと言えよう。罰則がないとはいえ、両党は法律を守るつもりがないのだろうか。産経新聞はこの事態について「順法精神のかけらもない」とばっさり切り捨てている。
自民党のある衆議院議員は今回の選挙戦で、ある女性候補者について、「(任期の)6年間の最大の功績は子どもを作ったこと」という応援演説を行ったが、党としての姿勢が如実に表れてしまっているように思える。
さらに深刻なのが公明党だ。公明党は昔から女性問題への取り組みには熱心だった。また、支持母体である創価学会の「婦人部」といえば、選挙戦で最強の精鋭部隊として名を馳せてきたし、また、人材の宝庫でもあったはずだ。しかし今回の選挙では公明党の女性候補はわずか2人である。いったいこれはどういうことなのか、理解に苦しむ。
非改選も含めた選挙前の参議院全体の女性比率はわずか20.7%である。もちろん、女性でありさえすれば誰でもいいなどというつもりはない(それぐらいは言われずとも「恥を知っている」)。だが、20.7%、わずか5分の1というのは、いくらなんでも低すぎるだろう。これをどこまで上げられるかが今回の隠れた焦点とも言えるのではないか。まさか、下がるなんてことは……ないですよね?