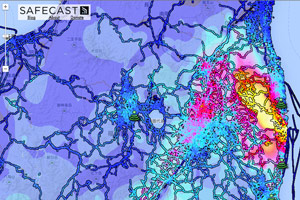誰が「被災地」を語ることができるのか
「震災」というものに対して、僕はいつも半端な立ち位置にいる。3.11当日は東京にいたので物理的被害は受けていない。その後石巻に移住して一年半ほど過ごしたが、海外留学を経て今は東京に帰ってきている。神戸出身ではあるが、阪神・淡路大震災当時は小学1年生で行動範囲も狭く、我が家の被害も小さかった。
直接の「被災者」ではもちろんないし、「支援者」という言葉もしっくりこない。あの日の震源地にたどり着くことはこれからも永遠にないし、かといって、波打ち際から完全に離れることもできない。わかりやすい足場を持たないまま、ときおりこうして筆をとる。
震災後の東北をめぐる言説には、数多くの対立や分断がつきまとう。外からの提言に対しては「よそ者に何が分かる」、内からの発信に対しては「勝手に被災地を代表するんでねぇ」。どんな言説も現実の一側面を切り取ったにすぎないから、そこに該当しない者からの違和表明はいくらでも起こりうる。
だけど、被害、補償、住居、仕事、世代、価値観、文化……あらゆる条件がバラバラな中、一片のためらいも異論もなく“正しい「被災地」”像を語れる人など、どこにいるだろうか。
「被災者」「支援者」「部外者」、「原発推進派」「反対派」といったカッコ付きの区分けが、その中に置かれる個人の心境には様々なグラデーションがあることを忘れさせ、立場を越えた共通の土台を覆い隠す。
半端者の僕は、どの枠組みにもフィットしない。だけど、枠組みを離れてこそ見えるものもあると思う。
「」(カッコ)が外れるまでの時間
もし、4年目のこの場で何か言えるとしたら、絡まった糸がほぐれるのには、長い時間が必要だということだ。そして、その道筋も複数の選択があるということだ。僕の場合は20年かかった。その過程で海も渡った。
震災後1年目の石巻では、「OCICA(オシカ)」という、鹿の角を漁網で編んだ手仕事商品のプロジェクトの運営に携わった。担い手となる牡鹿半島の浜のお母さんたちと、地元で協力してくださる方々と、外から来た僕たち若い世代と、色んな人が関わり合うから、当然一筋縄ではいかない。浜のお母さんたちの暮らしの被害も心の傷も、さまざまだった。でも、毎週みんなで集まって作業をして、終わったらお茶っこをして、笑って泣いての日々を過ごしていくうちに、一人ひとりの表情も心境も変わっていった。

撮影:Lyie Nitta
気づけば「OCICA」は不思議な家族のようなコミュニティへと育っていた。「地元民」か「よそ者」かなんてもはやどうでもよく、「被災地支援」でも「復興支援」でもなくて、もっと温度感のある関係性が紡がれていた。
季節は巡り、今に至るまで4度の3.11を迎えている。その過程で、浜のお母さんたちの傷を少しでも癒やすことができたならばとてもうれしい。だけど実のところ、みんなに癒され、ほぐしてもらったのはほかならぬ僕の方なのだったと思う。
当時、自身が神戸出身であることと、東北への関わりを、つなげて語ることを避けていた。生まれの話になればすぐ、「神戸の被災経験があったから東北に関わっているんですか?」などと一足飛びに結び付けられるのが嫌だった。たぶん冒頭で記したような「非当事者」としての遠慮もあったし、自分が受けた傷など大したことではないから、東北の人と一緒にしては失礼だ、などと考えていた。
だけど、数年かけて記憶をたどるなかで気付かされた。僕もやっぱり神戸の震災で傷ついていたのだと。周りへの遠慮と我慢、家族との距離感、地元なるものの煩わしさ、復興を巡る言説の圧力、どこかでいつも息苦しさを感じていた。
「第二のふるさと」、「石巻の父・母」と呼べるような人たちに囲まれて過ごし、そして日本から遠く離れたニューヨークへ渡ってはじめて、そのことを素直に受け止めることができるようになった。
そのときにようやく、東北で被災した人たちの痛みに、ほんの少しだけ触れることができたような気がした。同時に、生まれ育った神戸のことも、素直に祈れるようになった。
「被災者」「支援者」「部外者」――カッコ付きの肩書きで見れば違う立場だと分けられがちな人同士でも、一人ひとりが自分の内面を見つめていけば、きっとどこかで接点はある。だけどそれには、長い時間が必要なのだ。
僕は神戸と東北を経て、20年。東日本大震災は原発事故も引き起こした。多くの人のわだかまりと葛藤の糸がほぐれるまでには、気が遠くなるほどの長い時間が必要だろう。ほぐれないままの人生も、きっとある。
4年が経ち、記憶の風化を懸念する声も少なくない。それに抗うように、各地で慰霊やチャリティーのイベントが例年催されている。
それはそれで大切なのだけど、もしかしたらいま本当に必要なのは、わかりやすい「被災地支援」の物語ではなく、この葛藤はもっと複雑で長く続くのだという、ある種の「諦念」ではないだろうか。「被災地を忘れないために!」といった、カッコ付きで声高な呼びかけではなく、それぞれが等身大の個人として痛みと向き合う勇気ではないだろうか。
「何も復興の手伝いをできていなくて申し訳ない」
そんな風に言う人もいる。だけど、必ずしも何かアクションを起こしたり、具体的な活動を継続しなければいけないということはない。地元の人だってそうだ。震災を機にUターンをし、地元の復興のために奔走している人もいれば、「なんだかちょっと疲れちゃったのよね」と、途中でふるさとを離れる人もいる。僕はそれで良いと思う。
絡まった糸がほぐれるまでには時間がかかる。上から吊り下げられた「正解」ではなく、その時その時の自分の琴線に沿う単位で語ること。それを見つけるまでの時間と、ぎこちなさを、自分にも他人にも認めること。ときには休むことも重要だ。細く、長く、続ければいい。

撮影:Lyie Nitta
いつか、この子が大人になっても
昨日・一昨日と、福島県いわき市の小名浜にいた。この港町には少し年上の愉快な友人たちがいて、ひょんなことから、数カ月に一回通っている。知り合うきっかけや会話の内容には、もちろん震災やその後の活動の影響があるのは間違いないのだけど、僕は取り立ててこの地で「復興」のための何かをやっているわけではない。住む場所でもなく帰る場所でも働く場所でもなく、ふらっと訪ねて、飲んで泊まって、遊ぶ場所。それが小名浜。
昨年の秋、小名浜の友人夫婦のもとに新しい命が生まれた。もう5カ月になり、そろそろ離乳食かという成長ぶり。赤ちゃんって、すごい存在感だ。
一昨日の夜は久しぶりにみんなで食卓を囲んだ。時おり目を覚まして泣き出すその子のもとへ、代わりばんこに駆けつけてあやす友人夫婦の姿を眺めながら、同席していたもう一人の友人と酒を飲んでいた。
「この子もそのうち大きくなって女子高生とかになるわけですよ、そしたら僕も40ですよ」
「ねー、信じらんないねぇ」
震災直後の体験も記憶も、当然この子にはない。年頃になれば恋にオシャレに部活にと、夢中になるものがたくさんできるだろう(すでに視点がおっさんくさい)。だけど、神戸にいた僕と同じように、小名浜で生まれ育つというそれだけで、いやおうなしに「震災」の記録と記憶は彼女の人生にも差し込まれていくだろう。両親から、ローカル番組から、学校の授業から。彼女が大人になってもまだ、福島第一原発の廃炉は完了していまい。浜通り出身というだけで、何かのレッテルを貼られることもあるかもしれない。
彼女自身が、「震災」や「原発」や「地元」なるものにどう向き合い、どう受け止めていくのか、それは誰にもわからない。彼女が思い悩んだとき、おっちゃんになった僕に何が言えるかも、わからない。
ただひとつ実感があるのは、15年先も30年先も、僕は変わらず小名浜に通い続けているだろうということだ。ご近所さんでも親戚でもない、少し遠くのおっちゃんとして、この子の成長を見守り続けるだろうし、友人たちとは変わらず美味い日本酒と魚を囲んでいることだろう。それはすでに、そしてこれからも、僕の日常の一部なのだと思う。
撮影:鈴木悠平
東京に帰り、一夜明けて3月11日。変わらぬ日常。
この原稿を書いたら仕事へ行く。14時46分に黙祷することはできないだろう。メモリアルだからといって、針が止まるわけでもなく、毎日は続いていく。
風化? そうじゃない。
住む場所が離れていても、黙祷ができなくとも、みちのくの時間は僕の中に流れ続けている。
撮影:Lyie Nitta