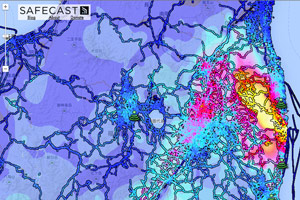「私がどこまで語っていいのだろうか」。
岩手県沿岸の街の中で最も南に位置している、陸前高田市。震災直後から通い続けることになったこの街には当時、夫の両親が暮らしていた。私は後から加わった家族であり、当時あの街にいなかった――つまり津波をこの目で見ていない――被災をしていない自分に、果たしてどこまで言葉を紡ぐ資格があるのだろうか。この4年間、常にそんな“後ろめたさ”を抱いてきた。
それでも大切なのは、その“後ろめたさ”から逃げないことだと、この街で、東北で教えられてきたように思う。ここから綴るのは、温かく迎えてくれた家族たちのこの4年間の軌跡を私の視点から見つめたものだ。
「どうやら東北で地震があったらしい」。
そんな情報を私と夫はそれぞれ、フィリピン、ザンビアという海の向こう側で受け取った。陸前高田は普段から揺れの多い地域だ。きっと大したことはないのだろう、と当初は思っていた。真っ黒な壁のような波が、街を次々飲み込んでいく映像を、テレビ越しに目にするまでは。
あの3月、帰国して目の当たりにした陸前高田の街は、そこにどんな営みが存在していたのか想像することさえできないほど、中心部がごっそりと流された状態だった。累々と広がる瓦礫の山を見つめながら、「生きていたら奇跡だと思おう」と低く夫が呟いた。
それでも義父は病院の4階で、首まで波に浸かりながらも、辛うじて屋上に逃れることができた。その波に飲まれるまでの写真が、なんと義父のカメラに残されていた。
撮影:佐藤敏通
撮影:佐藤敏通
撮影:佐藤敏通
県立高田病院に押し寄せてくる津波
「恐くなかったの?」と思わず尋ねる。
「それがね、まったく恐くなかった。目の前に広がっている光景があまりにも現実離れしすぎていて、実感が湧いてこなかったんだよ」
あの日、何とか助け出すことができた患者さんや避難者の方々と、寒空の下オムツやビニール袋を体に巻き付けて過ごしたそうだ。なぜここにいる以上の、もっと多くの人たちを助けることができなかったんだろう。医師として、副医院長としての自分を責めながら。
義父が救出されてから、私たちは義母の足取りを追った。平凡な義母の名前は、この小さな街の中で、いくつもの避難者名簿に見つけることができた。その度に私たちは喜んで、避難所に向かった。しかしそれは全て、同姓同名の別の避難者だった。震災から2週間ほど経った頃、その足は避難所ではなく、遺体安置所に向かうようになっていた。そして、その遺体安置所へ通う足も、だんだん重くなっていた。「生きている」という希望は既に手離していた。
撮影:安田菜津紀
震災直後の県立高田病院。がれきに阻まれ、近づくことさえ困難だった
義母が見つかったのは約1カ月後の4月9日、気仙川の上流を9kmも遡った、海などまったく見えない場所だった。義母は9km濁流に流され続けてもなお、家族のように大切にしていた2匹の犬の散歩紐を、しっかりと握りしめたままだった。
「例えばおにぎりが一つ足りなければ、自分は食べたつもりになって微笑む人でした」。葬儀の日、義父は義母の人柄をそう語った。彼女は生前、手話の通訳をしていた。今回の震災以前の地震でも、津波警報が出ると真っ先に、耳の不自由な方の元へ走ったそうだ。間もなく義父は、陸前高田に近づくことさえできなくなった。近づこうとすると手が震える、呼吸が苦しくなる。体が言うことを聞かないのだ。
やがてテレビや新聞の中は、「頑張れ、頑張れ」という言葉、そして「復興へ、復興へ」という勢いに溢れていった。その一つひとつが、とても尊いものだった反面、義父の心が次第に追い詰められていることが見てとれた。自分は頑張れていないからだめなんだ、復興の力になれていないのはいけないことなんだ、と。あの「頑張れ」という言葉の裏には、あまりにも大切なものを失って、声さえあげることができないたくさんの“沈黙”が存在しているのだと、義父の背中を見ながら噛みしめた。

撮影:安田菜津紀
震災から2年後。県立病院跡地に満開となった菜の花と、その花が好きだった義母と
あれから4年。2人が暮していた県立病院の官舎の跡地は、かさ上げ工事に伴い、土の下に埋まった。どこに手を合わせに行けばいいだろう、と私自身思うことがある。
「起きてしまった災害の規模はもう変わらない。でも妻がもし生きていたら、その後の生活はまったく違っていただろうな」。
身を寄せている栃木の親戚宅で、義父がふと、呟いた。
「でもそれってずるいって自分で思うんだ。自分だけよければいいって思ってるみたいで」
そんなことはない、と声を大にして言いたい。悲しみの深さは、愛情の深さなのだから、と。
“もう4年”なのか、“まだ4年”なのか、心の歩調は様々かもしれない。突然ふと心が、あの4年前に引き戻されてしまう瞬間が、それぞれにあるかもしれない。大切なのは悲しみを抱え続けている人が、後ろめたさを感じずに生きられること。どんなに時間がかかっても、自分のペースで生きられるようになること。そのときまで待ち続けるよ、というメッセージを、言葉で、写真で、発し続けたいと思う。