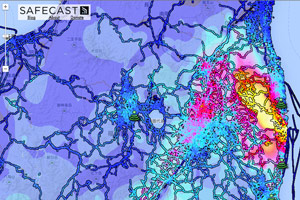インタビュー:津田大介 撮影:初沢亜利
2011年3月11日、津波に襲われた宮城県気仙沼で公民館が水没し、446人が取り残された。周りが火の海となるなか、絶体絶命の危機にさらされた彼らの危機は海を越えて情報が伝わり、やがてそれは奇跡的なリレーを果たし、感動的な救出劇につながった――。『救出 3.11気仙沼 公民館に取り残された446人』は彼らが全員救出されるまでの緊迫の状況を、迫真の筆致で描いたノンフィクションだ。執筆したのは東京都副知事(当時)としてこの奇跡の情報リレーのアンカーを務めたノンフィクション作家・猪瀬直樹氏。猪瀬氏にあの日気仙沼中央公民館でなにが起きていたのか、そこから導き出される今後の被災地復興のポイントを伺った。
気仙沼に行ったことがすべての始まりだった
――新刊の『救出──3.11気仙沼 公民館に取り残された446人』、興味深く拝読しました。東日本大震災当日、陸の孤島と化していた気仙沼市の中央公民館に、子どもたちをはじめたくさんの市民が取り残されているという情報が、ツイッターを通じて当時東京都副知事だった猪瀬さんに届き、東京消防庁のヘリに救出されたという奇跡のような実話です。このエピソードはさまざまなメディアで取り上げられましたし、猪瀬さんが震災直後に出版された書籍『言葉の力』でも触れられていますが、本書ではあの日気仙沼中央公民館でなにが起きていたのか、そこにはどんな人たちがいて、どうやってあの状況から「脱出」することができたのかが克明に描かれています。当然ハッピーエンドという「結末」は僕も知っていたわけですが、それでもこの本を読むと「現場ではそんなことが起きていたのか!」と驚かされることばかりで、ハラハラしながら一気に読み終えてしまいました。あらためて、この本を書こうと思われたきっかけを教えていただけますか。
猪瀬:震災から1年後の2012年の3月、あのとき気仙沼で助けた「一景島保育所」の所長さんと、障害児童施設「マザーズホーム」の園長さんが都庁を訪ねてきてくれたんですよ。そこで当時の経緯なんかをあらためて聞かせてもらったのですが、半年後に新しい施設が高台にできるから、落成式にぜひ出席してくださいと誘っていただいて。それで、鈴木さんにも声をかけたんです。
――鈴木さんというと……?
猪瀬:本の冒頭に出てくる、東京でオフィス家具の据え付け会社を経営している社長さんです。ほら、気仙沼のツイートを僕の元に届けてくれたのは彼だったから。
――ああ、あの鈴木さんなんですね。そもそも気仙沼市中央公民館の状況をツイッターでつぶやいたのは、障害児童施設「マザーズホーム」の園長である内海直子さんの息子・直仁さんだったんですよね。当時、中央公民館は津波が2階天井まで浸水し、火の海に囲まれてヘリコプターでしか近づけない状態でしたが、震災直後のパニック状態のなかで気仙沼市から宮城県への救援要請がうまくゆかず、公民館に避難していた市民446人が取り残された状態だった。そこで、内海さんが携帯メールでロンドン在住の息子さんに送った「公民館の屋根にいる」「火の海 ダメかも 頑張る」といった情報をもとに、息子さんが救助を訴えるツイートをツイッターに書き込んだ。そのツイートに目を留め、猪瀬さんのツイッターアカウントにコピペで転送した人物が鈴木さんだったと。
@inosenaoki 障害児童施設の園長である私の母が、その子供たち10数人と一緒に、避難先の宮城県気仙沼市中央公民館の3階にまだ取り残されています。下階や外は津波で浸水し、地上からは近寄れない模様。もし空からの救助が可能であれば、子供達だけでも助けてあげられませんでしょうか。
— 猪瀬さんに今後も期待します (@shuu0420) 2011, 3月 11
猪瀬:そう。鈴木さんは救出劇のきっかけをつくってくれたキーパーソンでしたが、気仙沼の人たちは彼の存在を知らない。僕が新しい施設の落成式に出席するなら、彼も呼ばなければならないと思ったんです。とはいえ、僕も鈴木さんとは面識がなかったから、まずはツイッターのDMを送って。
――猪瀬さんご自身で鈴木さんにDMを送ったんですか!?
猪瀬:うん。「気仙沼の保育園と障害児施設が復興するから、一緒に行きませんか?」って。それで、2012年9月、気仙沼で式典が開かれた日に初めて会ったんですよ。東京駅で待ち合わせて、同じ新幹線に乗ってね。
――それはすごい話ですね。では、東京から気仙沼に向かう道中、ずっと鈴木さんとお話をされたんでしょうか。
猪瀬:お互いに初対面で、僕のほうは鈴木さんがどういう人なのかもまったくわからなかったわけだから。「お仕事はなにをされてるんですか?」「なぜ僕にツイートを転送したんですか?」なんて質問してたら、自然と取材が始まったかたちになってしまって(笑)。鈴木さんはその日、パリっとしたスーツに身を包んで一流企業のサラリーマンのような出で立ちだったんだけど、じつはもともとヤンキーで、若くから働き始めて一時は仙台で事業を任されて、その間、気仙沼に遊びに行ってサンマの刺身を食べていたそうです。バブルの波に乗ってそれなりに成功したものの、バブル崩壊ですっからかんになって、それから地道に働いて8年かけて借金を完済して、起業。いまは複数の社員を抱える会社になった……みたいな話をずっとしていました。
――鈴木さんのドラマティックな半生はこの本のプロローグとして使われています。それだけでも一冊の本になりそうな鈴木さんの半生が導入部分に凝縮されていて、読者を引き込んだところで気仙沼の本編が始まる。実にうまい構成だなぁと思いました。鈴木さんとの出会いが本書を執筆する大きなきっかけになったんでしょうか。
猪瀬:鈴木さんと会ったこともそうだし、やっぱり2012年9月に気仙沼で落成式に参加したことは大きかったね。中央公民館のあった場所を歩きながらいろいろな人と会って話をしていると、どうしても一人ひとりの物語みたいなものが見えてくる。そうするとやっぱりそれらのストーリーを追いかけたくなりますよね。
――たしかに『救出』は被災の現場を描いた緻密なルポルタージュであるものの、登場人物たちの背景や、人となりがしっかりと描かれていて、群像劇として楽しむこともできました。
猪瀬:みんなたまらなく魅力的なんですよね。あと、子どもたちやお年寄りのみなさんにも感銘を受けました。中央公民館で孤立していた人たちのなかには、保育園の園児たち71名が含まれていたでしょ? 施設復興の記念式典でその子たちがみんなで踊ってくれたんですよ。踊りながら「猪瀬さん、ありがとう!」って。それ見て涙が出てきちゃってさ。お年寄りもたくさん来てくれて感謝の言葉を述べてくれました。「俺がしたことは、こんなに多くの人に感謝されることだったのか」と。あれはうれしかったですね。
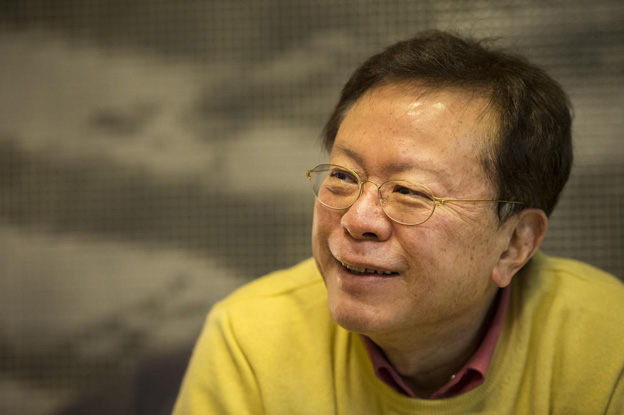
防災指南書としての『救出』
――中央公民館には、幼児や妊婦、お年寄りを含む466人の市民が取り残されていたわけですからね。建物を囲む火の海や度重なる余震におびえながら、公民館の限られたスペースで、電気も暖房も十分な物資もないまま凍えるような一夜を過ごした。そんな彼らにとって、夜が明けて救出のために現れた東京消防庁のヘリは、まさに希望の光だったのだと思います。逆に言うと、市民の目線で一晩の出来事を綴った本書は、生き残った人たちの貴重な証言集──「防災指南書」でもある。執筆するにあたりその点も強く意識されたと思うのですが、猪瀬さんが「防災」という観点から、あの救出劇で得られた教訓はなんだと思いますか。
猪瀬:まずは「瞬時の判断」と「毅然とした行動」でしょうね。じつは、3月11日の2日前、3月9日にも三陸沖を震源とする地震が発生していたんです。マグニチュード7.3、宮城県北部の震度は5弱と大きな地震で津波注意報も出ましたが、実際の津波は小さくて被害はほとんどなかった。それで、3月11日の地震発生時も「どうせ2日前と同じだろう」と油断してしまった人が少なくなかったんです。
――不運なことに、そのせいで「すぐに逃げる」という判断をせず、明暗が分かれたケースも多かったらしいですね。気仙沼だけでなく、陸前高田など、ほかの地域も同様の事例があった。2日前の地震が「予行演習」になった人もいれば、正常性バイアス――2日前大丈夫だったんだから今回も大丈夫だろうと思い込んで逃げ遅れて津波に飲み込まれてしまった人も多かったと聞いています。
猪瀬:そんななか、たとえば『救出』に登場する一景島保育所の所長・林小春さんは、日ごろの訓練通りに子どもたちを中央公民館に避難させることを即断しました。「時間との勝負だと思った」と、昼寝中だった4歳児以下の子どもたちが靴下を履く時間すら惜しんで、地震発生からわずか8分後には子どもと保母の全員を300メートル離れた場所にあった公民館へ移動させているんですね。
――14時46分に地震が発生し、津波が公民館の周辺に到達したのは15時30分ごろです。その間数十分ありますが、体感時間としては本当にあっという間だったでしょうね。
猪瀬:その数十分の間に、保護者が慌てて子どもたちを公民館まで迎えにくるわけですよ。「子どもを家へ連れて帰る」とね。そこでも、林所長をはじめ保母さんたちは毅然とした態度をとっている。「すぐに津波が来るから、保育所として子どもを帰すわけにはいきません」と、保護者も公民館に留まるよう説得し、車の中に置いてきた携帯電話を取りに戻ろうとする保護者にすら「外に出ないでください」とキッパリ言っているんです。保母さんたちは「すべてに『NO』を出すことで意思統一できていた」とのことですが、津波という危険が差し迫っているときは、この「厳しさ」こそもっとも大事なことなんだと思いますね。
――そして、公民館の2階に避難した子どもや大人たちを見て、近くで酒屋を営む男性が「ここじゃダメだ!」と叫ぶ。あの判断もすばらしかった。
猪瀬:「もっと上さあがれ!」と言うんだよね。それで子どもたちをはじめ全員が最上階の3階へ移動するんだけど、結果的に津波の第一波が2階の天井まで浸水するわけだから、その判断は正しかったということになる。あそこで3階に上がらなければ2階にいた人はみんな津波に飲まれていたでしょう。
――その後、第一波よりも高い第二波、第三波が来るかもしれないという恐怖のなかで、全員が3階の屋上に出ます。寒さ対策のため、子どもたちには階下からもってきたカーテンをかぶせて。でも、それでも安心できないということで、今度は梯子をのぼって立ち入り禁止区域の屋根にまであがるわけですが、梯子の形状や人の動きが細かく描かれていて、まるで映像を見ているみたいに光景が頭のなかにスッと入ってきましたね。
猪瀬:“おんぶ作戦”のくだりだね。屋根の上にのぼるには点検用の鉄梯子を使うしかなかったから、男性たちが乳幼児をひとりずつおんぶして屋根に上げた。時間がかかるし、体力も相当消費するけれど、とにかくやった。そうしてしばらく屋上にいたら、夜になってみぞれが雪に変わり、寒さが深刻になってきた。それと同時に周囲の「海上火災」が勢いを増して、真っ黒な煙に包まれて。寒さに煙に火の海に、それから津波の恐怖。もうみんな極限状態なんだよね。それで、ここでまたひとつ決断を下すわけです。おそらく、これ以上津波の水位があがることはないだろうということで、3階の屋内に戻ろうとする。
――せっかく屋根の上までのぼったのに、また“おんぶ作戦”で今度は下に降りるんですよね。しかも、暗いなか梯子を降りれないお年寄りに配慮して、屋上の屋根を壊して屋根裏に避難させてくれた人もいた。この本を読むまでは避難者のみなさんが屋上で夜を明かしたと思っていたので驚きました。ここで屋内に戻るという判断をしたことも全員が助かる大きなポイントだったのかなと。
猪瀬:そうでしょうね。ただ、屋内に戻ったといっても、3階のスペースはものすごく狭いから、466人が入るともうすし詰め状態で。全員が座ることはできない。男性の多くは立ちっぱなしだったんです。しかもいつ救助がくるかもわからない。本にも書いたけど、まさに「人生で一番長い夜」ですよ。

――そんな状況のなか、「マザーズホーム」の内海さんが携帯電話から送った「公民館の屋根にいる」「火の海 ダメかも 頑張る」というメールがロンドンの息子さんまで届くわけですよね。
猪瀬:そう。地震発生後、しばらくは携帯電話のメールだけは使えたから、中央公民館にいたほかの人たちもそれぞれ外に向けてメールを送っていたはずなんですよ。でも、あたり一帯停電になると携帯電話の基地局の非常用電源も数時間で落ちて機能しなくなる。それによって携帯のメールも届きにくくなったんですが、それでも届くメールがいくつかあって、そのうちのひとつが内海さんのメールだったんですね。
――息子さんはロンドンでUstreamの中継やツイッターの画面に張り付いて、なかなか返ってこない家族からのメールにやきもきしながら、非常時にどういう行動を取ればいいのかをメールで何度もアドバイスしています。母親が公民館にいるのはわかっている。PCの画面に映し出される気仙沼の空撮中継は激しい火に包まれている。やがて家族や母親からのメールもパタリと途絶えて、「もしかしたら中央公民館に子どもたちが取り残されていることを知っているのは、世界中で自分だけかもしれない」と考えるようになるんですよね。この状況を人に知らせる方法はないか──それで、ツイッターの画面を開く。
猪瀬:ツイッターには140文字という文字制限があるから、そのかぎられた文字数のなかで起きている事態を緻密かつわかりやすく説明しないといけない。彼はひとつのツイートの文章をつくるのに30分以上時間をかけているんだよね。
――そうして完成したツイートが以下の通り。息子さんは当時まさか466人もの市民が避難しているとは知らず、避難者数こそ誤認しているものの、全体的に非常に論理的でわかりやすい文章です。これが鈴木さんの目に留まり、その後、猪瀬さんに届けられて事態を動かすことになります。
>障害児童施設の園長である私の母が、その子供たち10数人と一緒に、避難先の宮城県気仙沼市中央公民館の3階にまだ取り残されています。下階や外は津波で浸水し、地上からは近寄れない模様。もし空からの救助が可能であれば、子供達だけでも助けてあげられませんでしょうか。
「必然の偶然」が起こした奇跡
猪瀬:さっき、2012年9月に気仙沼を訪問したことが『救出』を書くきっかけになったと言ったけれど、じつはもうひとつあって、それが内海さんの息子さんとの出会いなんですよ。2012年の夏にロンドン五輪があったでしょう? 当時、僕は東京五輪の招致に向けて活動している最中だったから、ロンドンまでオリンピックを視察しに行ったわけ。「そういえば気仙沼のツイートをしてくれた息子さんがロンドンに住んでいたな」ということで、どうせ行くなら会えないかなと思った。それで連絡先を調べて連絡したら会えることになったんです。
――猪瀬さんのなかで彼はずっと気になる存在だったんですね。
猪瀬:だって、「そもそもなんでロンドンにいるのよ?」とか、聞きたいことがたくさんあったから。実際に会ってみると彼は30歳手前の青年で、ロンドンのハットン・ガーデンという宝石店が軒を連ねるエリアで自分の店を営んでいた。宝石店街といってもカルティエみたいなハイブランドのジュエラーはなくて、どの店にもショーケースの裏には工房がある。日本でいうと昔の骨董通りとか秋葉原みたいな雰囲気かな。しかも、そこにいるのは商人も職人もユダヤ人ばかり。つまり、内海さんは若いころからユダヤ人たち相手にビジネスをしてきたんです。それを知って、あのツイッターの論理的な文章はビジネスで磨かれたものなんだと納得したんだけど、それでもやっぱり「気仙沼」と「ロンドン」が自分のなかでつながらない。
――東北の小さな町からなぜロンドンへ渡ったのか、その理由が見えなかった。
猪瀬:そうそう。それで話を聞いてると、18歳のときに当初は靴職人をめざしてロンドンへ渡ったと言うんだよね。高校は岩手県の一関にある高専に通っていて、5年のうち3年でやめてロンドンへ来ちゃったと。気仙沼から岩手の高専へ通っていた高校生が、学校を辞めて仙台でも東京でもなく海を渡ってロンドンへ行っちゃった。ますますわけがわからない(笑)。
――たしかにそうですね。しかもツイートを読めばとても理性的なことがわかるし、ビジネスもうまく軌道に乗せている。
猪瀬:でも、本人に会って話を聞いているうちに、お父さんが船乗りをしていたと教えてもらってピンときたんですよ。船乗りといっても漁船ではなくて、タンカーみたいな大型貨物船の船員だったんだよね。幼いころから父親はいつも外洋にいて、たまに「日本へ帰るぞ」と連絡があると、家族で横浜港や神戸港へ会いにいっていたそうです。そこで数日の休暇をともに過ごし、サンフランシスコやロサンゼルス、シドニー、ロンドンといった海外の都市の話をたくさん聞いていたんですよ。
――なるほど。息子さんにとっては、父親の影響もあって幼いころから海外が身近な存在だったと。
猪瀬:その話を聞いたときは僕も「なるほど、父親の影響ね」と思った程度だったんだけど、1カ月後に施設の式典で気仙沼へ行ってみたらそれが良い意味で裏切られたんです。「彼が言っていたのはこういうことだったのか!」と衝撃を受けた。どういうことか。内海さんだけが特殊な環境で育ったわけじゃなくて、港町である気仙沼自体が「外に開かれた街」だったんですよ。
――それはもしかして気仙沼港が遠洋漁業の基地だからですか?
猪瀬:そう。気仙沼は内海さんとこのお父さんみたいに海運会社で働く人たちのほかに地元の遠洋漁業も盛んで、漁師のおやじさんたちは気仙沼からインド洋や地中海、果てはチリの南氷洋近くまで行ったりして、世界中を航海しているんですよ。地元の居酒屋に行ってみると、鹿児島や高知から寄港中の漁師が肩を並べて酒を飲んでいたり、なぜかスペイン語をペラペラ話すおやじがいたり。
――漁港がハブになってるんですね。気仙沼の人たちは日本中や世界中に出ていくし、逆に気仙沼には日本中や世界中から人が集まってくる。
猪瀬:もうひとつ驚いたのが、昼食で寄った被災した割烹の仮設テントでの出来事なんです。そこで大きなサンマの定食を食べていたら壁に被災前の店の写真が飾ってあった。昭和4年創業の老舗とのことで、店に灯籠があったりして、赤坂あたりの料亭みたいな良い雰囲気を醸し出しているんですよ。で、その店の名前はなにかというと、割烹「世界」って書いてある。昭和4年に「世界」だよ?
――その時代にその店名を付けるのは、かなりハイカラなセンスですよね。
猪瀬:そうか、ここは昔からそういう場所だったのかと、目から鱗が落ちる思いでした。僕がそれまで気仙沼という地名から連想していたのは「三陸地方」──「陸」という言葉だったんだけど、そんなのは明治時代の行政区分であとからつけられたものなんですね。それで、自分が「陸地視点」で三陸を見ていたことに気づかされた。陸地である日本列島をポジにして、海洋をネガにすると、三陸地方はきわめて孤立した僻地に見えるけれど、海洋をポジに、陸地をネガにすれば見え方が全然違ってくる――要するに、気仙沼は世界とつながっているんですよ。
――海洋視点で気仙沼を見れば、じつはものすごいグローバルシティだったと。そこで育った内海さんがロンドンへ渡るのはなにも不思議なことじゃないですね。
猪瀬:そう。だから今回、いろいろな人に話を聞くなかで見えてきたひとつのテーマは「必然の偶然」ということなんです。
――必然の偶然……?
猪瀬:まず、たまたま気仙沼の魚市場や製氷工場、工務店なんかが集まっている職人の多いエリアの人たちが近くにあった公民館に避難した。そこで“おんぶ作戦”をはじめみんなが各自の能力を発揮して生き延び、たまたま内海さんの携帯メールがロンドンに住む息子へ届いた。なぜ息子がロンドンにいたかというと、気仙沼が昔から外に開いた街だったから。しかもその息子は、ロンドンでユダヤ商人相手にビジネスをするなかで磨いたロジカルシンキングを身につけていて、その能力を発揮して自分の母親の状況を知らせるツイートをした。それに目を留めたのが気仙沼にも住んだことがある元ヤンの鈴木さんで、彼が何か気仙沼のためにできることはないかと思って僕に転送した。僕はたまたま民間出身の副知事でそのときツイッターを積極的に使っていた。僕がツイートを見て最初に相談した東京消防庁の防災部長は、判断能力と実行力に長けた人物だった――これらすべては偶然の連鎖なんだけど、その偶然を一つひとつつなげていくと、必然的な流れだったことが見えてくるんです。
――なるほど。『救出』で描かれているのは、「必然の偶然」が起こした奇跡の救出劇だったわけですね。たしかに、どれかひとつの偶然が欠けていたら、同じ結果にはならなかった可能性は高いですね。職人さんたちがいなければ、雪が降るなか屋上で低体温症にかかって亡くなる方が出ていたかもしれないし、内海さんの携帯メールがつながらなければロンドンの息子さんが状況を知ることもなかった。息子さんのツイートがいい加減なものだったら人の目に留まることもなかっただろうし、副知事が猪瀬さんじゃなければ被災自治体からの正式な救出要請がないのに独自の判断でヘリを出すということはしなかったかもしれない。
猪瀬:本当にそうなんだよね。気仙沼に行って「ここはグローバル都市なんだ」と気づいた途端、それまでは点と点だった偶然がひとつにつながり、その瞬間「このことを本を書こう」と決めたんです。

リーダーでなく「現場力」に頼る
――『救出』を読んでいて印象的だったことのひとつが、先ほど猪瀬さんがおっしゃった「みんなが各自の能力を発揮して生き延びた」という点です。たしかに本書では、屋上の立ち入り禁止区域に入る際、人よけのフェンスを崩したり、鍵を壊す人がいたかと思えば、屋上に簡易トイレをつくる人がいたり、屋根の上から屋内に戻るにあたって梯子を降りれないお年寄りのために屋根を壊して屋根裏に避難できるようにしてくれた職人もいる。また、満員電車状態の3階で朝を待つようになってからは、わずかな水をペットボトルの蓋に入れて1杯ずつ分け合う“ひと口ルール”が徹底されるなど、チームワークが機能していました。それが全員が生き延びることができた大きな要因でもあるわけですが、あの極限状況でチームワークがうまく機能したのはなぜだとお考えですか?
猪瀬:それについては僕もいろいろ考えたんだけど……たぶん、リーダーが不在だったからうまくいったと思うんですよ。
――リーダーの不在がチームワークにつながった……!? それはどういうことでしょうか?
猪瀬:もちろん、保育所の林所長や元高校野球児の青年など、要所要所で大きな判断を下す人はいたんだけど、突出したリーダーシップをもつ人はひとりも登場しないでしょう? 僕はそれが逆に良かったと思うんだよね。公民館という沈没寸前の船に乗った466人の乗組員が、必死にそれぞれの持ち場を守って沈没を防いだんですよ。
――それは興味深いご指摘ですね。非常に厳しい状況のなか、466人もの人たちが協力し合い、リーダー不在でも困難を克服した。少なくともあの日の中央公民館ではそれができた。この成功事例は、今後の震災復興を進めていくうえでのひとつの教訓になるような気がします。
猪瀬:要するに、日本はもともとリーダー不在の国なんですよ。太平洋戦争だってそう。結果として大敗したけれど、個々の戦場──硫黄島や南洋の島での戦いでは、もとはお百姓さんだったり職人さんだった兵士たちが、体を張って最後の最後までがんばるわけですよ。現場レベルではそれぞれによく工夫して戦っているのに、そもそも参謀本部のエリートたちの出す方針が間違っていたりする。
――それって、つまり「日本人は現場力が高い」と言い換えることもできますね。
猪瀬:そうそう「現場力」。日本は昔から「現場力」が優れている一方で、トップによる大きな方針決定や意思決定のもとではそれがうまく活かされなかったりする。『昭和16年夏の敗戦』にも書いたけれど、太平洋戦争だって優秀な若手官僚たちによる事前のシミュレーションで、おそらく負けるであろうことがわかっていたんですよ。みんな内心では「やめたほうがいい」と思っていながら、トップが一度決めるとやる方向に邁進してしまう。とはいえ、いまも昔も縦割り行政だから、現場の意見を汲み上げるのはむずかしいんですよね。
――ではやはり、震災から4年が経っても困難な状況が続く被災地で、その困難を突破していくためには、できるだけ権限を現場に移譲していく必要があると。
猪瀬:そうでしょうね。リーダーシップには頼らず、現場が力を発揮できるようにする。ただ、みんながまとまるにはそこにひとつの「目標」が必要になる。たとえば5年後、7年後の目標をもつことで、未来の自分はなにをしているんだろうという「歴史認識」が生まれますよね。最近の若いひとはそこが弱い。先日、25歳くらいの子と話をしていたんだけど、彼が生まれてからいままで日本のGDPはずっと横ばいで、おそらくこれから先も同じだと。だから昨日も今日も明日も、その先もずっと同じ日が続くと言うんですよ。それでは「歴史認識」が生まれないんだよね。
――古市憲寿さんの本にもなっている、いわゆる「絶望の国の幸福な若者たち」ですね。
猪瀬:若い人たちには不満がない代わりに欲もない。「歴史認識」をもって数年先のことを考えると、欲が出てくるわけだから。
――おっしゃることもよくわかるのですがあえて反論すると、いまの東北の若い人たちは「歴史認識」をもっているんじゃないかと思うんです。あの震災は、体験した前後では人生観すらガラリと変わってしまうほどのインパクトをもっていたと思います。
猪瀬:それは僕も同意します。「震災前」「震災後」という言葉は、「戦前」「戦後」と同じような意味をもっているはずです。
――あとは、彼らと同じ意識をほかの地域の人間がどのように持てるかということで復興の進み具合も変わってくるんじゃないかと思います。例えば東京の若い人はこれから「歴史認識」を持つことができますかね……?
猪瀬:東京五輪があるでしょう。とにかく、2020年には東京でオリンピックが開催されることが決まっている。これは国家目標だから、自分はオリンピックになんらかのかたちで関われるんだろうかとか、関わらなくても自分はそのときになにをしているんだろうかとか、いろいろなことを考えるわけです。オリンピックを単なるスポーツの祭典と捉えるだけでなく、ぜひ個人的な指標のひとつにしていただきたいですね。
――おっしゃる通りだと思う一方で、東北の人たちからは「東京五輪に建設リソースが奪われて被災地の復興が遅れる」といった不満の声も聞かれます。そうした声についてはいかがですか?
猪瀬:いや、確かにそういう側面はあるんですが、東京にたくさんの外国人観光客が来れば、それは結果的に地方まで足を運んでくれるんですよ。いまも北海道のスキー場なんかは海外からのお客さんでいっぱいですよね。オリンピックによって田舎の温泉地でも同じことが起こりうる。日本はこれから人口減少社会を迎えるけれど、毎年2000万人の中国人観光客が来てくれれば、温泉はつねに賑わいますよね。その意味では、2020年のオリンピックは名前こそ「東京五輪」だけど、「日本オリンピック」だと考えてほしいんです。日本にやって来た人たちにいかにしてお金を落としてもらうか、そのことを各地方で施策を講じればいいんじゃないかなと。
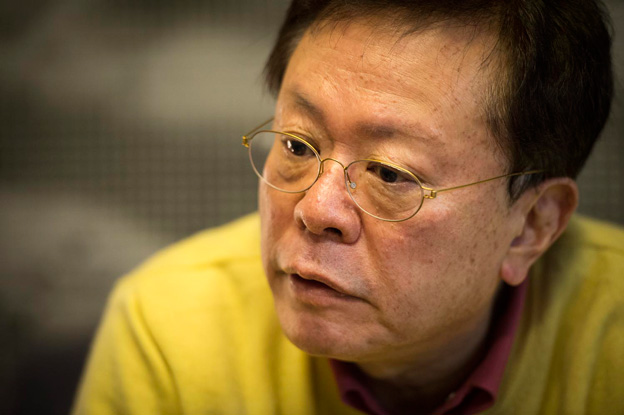
――復興の目標を東京五輪に定めることで、具体的に復興をイメージできるようになる。それが重要だということですね。よくわかりました。最後に猪瀬さんご自身の今後の目標についても教えてください。
猪瀬:そうだなぁ……。この1年で『さようならと言ってなかった わが愛 わが罪』と『救出』を書きました。この2冊を書く行為はいまの自分にとって絶対に必要なものだったと思います。これからまた雑誌の連載も始まるし、書かなければならないことはたくさんあるんだけど――。ただね、やっぱりね。……いやー、くたびれたね(笑)。
――歯に衣着せぬ物言いこそが猪瀬さんの売りじゃないですか!(笑)。元気出してくださいよ!
猪瀬:この数年でいろいろなことがありすぎたからね(笑)。今後は次の作品を書くことと、あとは僕の経験を若い人たちに伝えていきたいと思ってます。『さようならと言ってなかった』は亡き妻のことを書いた本だけど、そもそも僕はなぜ作家になったのか、無名のフリーライターからキャリアをスタートして、妻と二人三脚でいかにここまでやってきたかということを全部つまびらかにしている。そこは物書き志望の若い人に参考にしてもらえる部分があるんじゃないかなと思う。一方で『救出』も、なぜこの救出劇がうまくいったのかがわかるように書いたつもりです。

――以前、東北大学の教授が言っていたんですけど、東日本大震災の津波からの生存例については、とにかく「九死に一生を得た」みたいなスリルのあるものばかりがニュースになって注目されていたと。でも、「九死に一生」って良くない例で、そうではなく本当は大きな危険もなく命が助かった例にスポットを当てないといけないんですよね。
猪瀬:たしかに、「大変だった」という話はよく耳にするけれど、「うまくいったね」という話はそれに比べると少ないんだよね。「物書きがもっと成功例をきちんと書けばいいのに」とは思っていました。
――先ほどのお話にあった「必然の偶然」につなげて言えば、さまざまな偶然のリレーを最後に受け取って466人を救った副知事の猪瀬さんは“たまたま作家でもあった”わけですよね。作家だったからこそ優れたルポルタージュであり、貴重な防災指南書にもなる本書を人々の記憶が薄れないうちに書き上げることができた。じつは『救出』の出版をもってこの「必然の偶然」の連鎖が完成したんじゃないか──今日のお話を聞いていて、そんなことを思いました。
猪瀬:本当はもう少し早く書きたかったんだけどね。気仙沼を訪問したあと、書き始めてすぐに都知事になって、そこからはオリンピック招致に向けてバタバタの毎日が始まったから、執筆が頓挫してしまった。その後、いろいろあって知事を辞めて、こうして再び原稿に向き合う時間ができたわけで。本当に、人の人生なんてなにが起こるかわからないものです。