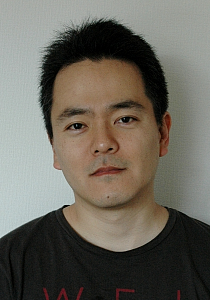【撮影:初沢亜利】
◆「ポイント・オブ・ノー・リターン」
「ポイント・オブ・ノー・リターン(引き返し不能地点)」――今回の沖縄県知事選挙の結果に、この言葉を思い出した。
沖縄がまだ米軍統治下にあった1968年12月に、当時国務省の日本担当をしていたリチャード・スナイダーが出張先の沖縄から国務省に送った報告に出てくる言葉である。
約1カ月前の11月10日、沖縄では初めての琉球政府行政主席(現在の知事)の選挙が実施された。琉球政府行政主席はそれまで米占領軍トップの高等弁務官の任命制だったが、沖縄県民の強い自治拡大の要求をアメリカも無視できなくなったのであった。
選挙には、保守陣営から那覇市長だった西銘順治氏、革新陣営から屋良朝苗氏が出馬した。アメリカは「即時無条件全面返還、米軍基地撤去」を公約に掲げる屋良氏の当選を阻止するために、日本政府・自民党と結託して様々な介入を行った。アメリカは表の経済援助だけでなく、裏でも自民党を通して西銘陣営に巨額の選挙資金を供与し、「基地が撤去されれば、琉球の社会は再びサツマイモと魚に依存したハダシの戦前の経済に逆戻りすることになる」(アンガー高等弁務官)と県民を脅した。
こうした米日両政府のなりふり構わぬ介入にもかかわらず——いや、介入はむしろ県民の反発を生み——選挙では屋良氏が西銘氏に約2万8000票差をつけて当選した。
スナイダーはこの沖縄の状況を「我々は返還問題で『ポイント・オブ・ノー・リターン』まで来てしまった。日本でも沖縄でも圧力が高まり、返還時期の決定をのらりくらり引き延ばすことは現実に期待できなくなった。とくに厄介なのは屋良選出後の沖縄の成り行きだ」と国務省に報告している。
さらに、こうも付け加えている。
「沖縄返還の方式における新しい要素は、沖縄で強まりつつある返還に向けた圧力である。過去には、ビッグ・ボーイズ(アメリカと日本政府)が問題を処理し、沖縄の人間は両国の決定を素直に受け入れるというのが我々と日本政府の暗黙の想定だった。だが、この想定はもはや当てにならない。返還交渉への沖縄側の割り込みが二通りのやり方でなされうる。一つは、扇動によるもので、それは公然たる米軍との衝突に発展しかねない。もう一つは、新行政主席となった屋良の大義に基づく熱い圧力を通じてだ」(新原昭治『日米『密約』外交と人民のたたかい』より)
この選挙結果は、沖縄返還を「のらりくらり」と先延ばしにしようとするアメリカのたくらみを打ち砕いた。翌1969年11月、ニクソン米大統領と佐藤栄作首相は1972年に沖縄を日本に返還することで合意する。

【撮影:初沢亜利】
◆決断の先送りは問題解決を困難に
今回の知事選挙の結果は、日米両政府にとって、辺野古移設見直しの「ポイント・オブ・ノー・リターン」だろう。勝負はついた。日米両政府はすぐにでも、辺野古移設に替わる「プランB」の検討・交渉に入るべきだ。
菅官房長官は、辺野古移設を「粛々と進める」と語ったが、このまま辺野古新基地建設をごり押ししても、沖縄県や名護市との行政上司法上の衝突、現場での県民との直接的な衝突は避けられず、早くても2023年完成という現在の計画は遅延に遅延を重ねるのが必至だ。それは、アメリカ自身が「世界一危険な基地」と認めた普天間の返還もそれだけ遅れることを意味する。
翁長氏が「普天間で大きな事故が発生したら、日米同盟、日米安保体制は吹き飛んでしまう。今は、偶然という『砂上の楼閣』の上で日々成り立っている」と指摘する通り、「普天間の固定化」は日米同盟を維持・強化しようとする日米両政府にとっても最悪のシナリオといえる。
そうであれば、日米両政府にとって残された選択肢は、現在の日米合意を見直し、辺野古新基地を断念し、普天間も早期に閉鎖・撤去する道しかないだろう。決断の先送りは、問題の解決をより困難にするだけだ。

【撮影:初沢亜利】
いずれにせよ、ボールは沖縄県民から日本政府に投げられた。翁長氏の言葉を借りれば、ここから先は、まさに「日本の民主主義のあり方、品格が問われる」のだ。
これに対する本土の私たちの応答としては、まずは、きたる総選挙で意思を示すことだ。解散した安倍首相も、選挙の争点は「安倍政治」に対する審判だと話している。つまりこれは、沖縄県民が知事選でこれだけ圧倒的な民意を示したにもかかわらず、辺野古新基地を「粛々と」進めていくと宣言している安倍政権に審判をくだすチャンスということだ。
そもそも、国の安全保障の問題は国民全体で考えるべきだし、必要な負担があれば、できる限り平等に分かち合うのが、本来の民主主義国家としてのあり方だ。国土のわずか0.6%の面積の沖縄県に74%の米軍専用基地を集中させている現状は、一刻も早く正さなくてはならない。同時に、必要のない負担は、分かち合うのではなく無くすべきだ。きたる総選挙でも、この問題を争点化し、沖縄に限らず全国で議論を起こしていかなければならない。
その際、少なくても「事実」として共有しておきたいのは、次の三つの点である。
◆実体なき「抑止力」
第一は、「沖縄の海兵隊は『抑止力』として不可欠」という政府の説明には根拠がないということである。
日本政府は沖縄の海兵隊の必要性を、国民向けには、一貫して「抑止力」という言葉で説明してきた。しかし、沖縄に駐留する海兵隊という戦力が具体的にどのような脅威に対して「抑止力」として機能し、沖縄に存在していなければならないのか、という説得力のある説明はこれまでされたことがない。
なぜなら、沖縄に駐留する海兵隊の性格や規模からいっても、そんな説明は不可能だからだ(これについては、すでにこのポリタスで元防衛官僚で内閣官房副長官補まで務めた柳澤協二氏が解説しているので、詳しくはそちらを参照していただきたい)。

【撮影:初沢亜利】
1970年代、アメリカが沖縄から海兵隊を撤退させ、米本土(カリフォルニア州)の部隊に統合することを検討していたことが、昨年、沖縄国際大の野添文彬講師(国際政治史)が入手したオーストラリア外務省の公文書により明らかになった。
しかし、撤退は日本政府の引き止めによって実現しなかった。同氏が入手したアメリカ国務省の当時の公文書には、日本政府が引き止める理由として、沖縄の海兵隊を「日本に対する直接的な脅威に即時に対応するアメリカの意思と能力の最も目に見える証拠」と見なしていることが記されている。
。
わかりにくいが、つまり、沖縄の海兵隊はアメリカが日本を守る「象徴的存在」なのだと主張しているのである。その後も日本政府は、沖縄の海兵隊の存在が「日本防衛のために、いつでもアメリカが立ち上がるという意思の確証を与える」(防衛庁)として、常駐の必要性を米側に訴え続けた(「琉球新報」2013年11月10日)。
これは、どこかの国が日本に侵攻して海兵隊員が殺りくされたら、アメリカは必ず報復・反撃するという「在沖海兵隊〝人質〟論」にも通じた考えだ。しかし、仮にそうだとしても、日本に常駐するすべての米軍部隊に当てはまることで、海兵隊や沖縄でなければならない理由は存在しない。
鳩山由紀夫元首相が「辺野古しか残らなくなった時に理屈付けしなければならず『抑止力』という言葉を使った。方便と言われれば方便だった」と語ったように、また、森本敏氏が防衛大臣を退任するに当たり「(普天間の移設先は)軍事的には沖縄でなくてもいいが、政治的に考えると沖縄が最適だ」と告白したように、「抑止力」の観点からも沖縄に海兵隊を置かなければならない理由はないのである。
私たちは、政府の使う「抑止力」という言葉で思考停止をしてはならない。
◆日米安保に関する大きな誤解
第二は、これもけっこう「誤解」している人が多いのだが、日本は一方的にアメリカに守ってもらっているのではない、ということである。
安全保障の問題を考える時に「抑止力」という言葉で思考停止してしまう要因に、「アメリカに守ってもらっているのだから、あまり大きなことは言えない」というメンタリティがあるような気がする。しかし、これは正しくない。
外交や安全保障はリアリズムの世界だ。アメリカだって、ただ一方的に日本を守るために60年以上日本に基地を置くほど「お人好し」ではない。それが十分、アメリカの「国益」になるからやってきたのだ。日米安保体制をアメリカ側から見れば、世界戦略上不可欠な基地を日本国内に置かせてもらう替わりに、日本を侵略する国があれば自衛隊と共に戦うことを保障しているのである。
かつて陸上自衛隊のトップ(幕僚長)を務めた冨澤暉氏も、公益社団法人「安全保障懇話会」の会誌(2009年2月)で次のように述べている。
〈「日本の防衛は日米安保により米国が担っている」と考える日本人が今なお存在する。しかし、在日米軍基地は日本防衛のためにあるのではなく、米国中心の世界秩序の維持存続のためにある、という現在では当然のことを国民に説明して欲しい。〉
また、1970年の米上院外交委員会で当時のジョンソン国務次官は、「アメリカは日本の直接の防衛に関する通常兵力は、いかなる地上または空軍の兵力も持っていない」と証言している。
日本は、アメリカに基地を提供するだけではなく、基地の運用に必要なインフラや労働力を提供し、それ以外にも、米同盟国の中で群を抜いた駐留経費負担(思いやり予算)を出している。また、日本防衛の第一義的な責任は日本にあり、これは在日米軍基地の防衛も自衛隊が担っていることを意味する。

【撮影:初沢亜利】
こうした「ギブ・アンド・テイク」で成り立っているのが日米安保体制であり、日本は戦後、徐々に基地提供以外のアメリカへの「ギブ」を増やしてきたのである。日本はけっして安保に「タダ乗り」しているわけではない。「一方的に守ってもらっているから……」などと卑屈になる必要はまったくないのだ。
日米安保条約は終戦6年後の1951年に、主権回復のサンフランシスコ講和条約とセットで締結された。この時、アメリカが最も重視したのは、「われわれが望むだけの軍隊を、望む場所に、望む期間だけ駐留させる権利」(ダレス国務省顧問)を確保することであった。戦勝国として占領下で獲得した基地の既得権を、日本が主権を回復したのちも、安保条約によって維持しようとしたのである。
この戦勝国ー敗戦国という関係性、そして、軍隊を解体されて安全保障をアメリカにゆだねざるをえなかった当時の関係性を、63年経っても引きずっているのが現在の日米安保体制である。
アメリカと安全保障同盟を結ぶということは、どんな基地でもアメリカの要求どおり認めるということとイコールではない。そもそも、歴史的に、独立国家に外国軍隊の基地が置かれるのは「特異」なことだ。米軍の中でも優先度が低く、「抑止力」の実体もない沖縄の海兵隊は、米領内に撤退するよう要求してもいいのではないか。
その場合、おそらくアメリカは、グアム移転費用以上の財政支援を強く要求してくるだろう。海兵隊が日本国内にこだわる理由は、日本に置いておいた方が思いやり予算もあり「安上がり」という事情もあるのだ。アメリカでは、財政赤字解消のために軍事費の大幅な削減が必至となっており、連邦議会では海兵隊の存在意義に疑義を唱える声もあがっている。辺野古新基地は海兵隊の〝生き残り策〟という側面もあるのだ。
◆沖縄の海兵隊がやってきたこと
第三は、沖縄の海兵隊は、日本の防衛と直接関係のないアメリカの戦争に実際に投入されてきた、という事実である。
沖縄の海兵隊は、ベトナム、アフガニスタン、イラクなど、アメリカがアジア・中東で行ってきた数々の戦争に投入されてきた。かつてのソ連や現在の中国といった大国相手に「抑止力」を発揮することはない一方、その即応性と機動力から使い勝手よく実戦に使われてきたのが、在沖海兵隊の歴史である。

【撮影:初沢亜利】
数年前、沖縄で日米地位協定の取材をしていた時、読谷村で出会った男性の言葉が忘れられない。
男性は定年まで約40年間、嘉手納基地で軍雇用員として働いた。基地について尋ねると、こう答えた。
「複雑だよね。自主経済ができていなかったから、米軍基地で働くしかなかった。この辺りは、期間の長い短いはあっても、大抵の人は基地で働いた経験を持っている。軍雇用員は、生活のために今すぐ基地がなくなったら困るけど、みんなずっとこのままでいいと思ってるわけじゃない」
定年で退職後、夫婦で初めて海外旅行に行ったという。行き先に選んだのはベトナムだった。
「自分が働いていた嘉手納から、B52(爆撃機)が爆弾積んでベトナムに飛んでいったからね。あの時の嘉手納には化学兵器もあった。そういうのもあって、仕事を辞めたらベトナムに行って手を合わせたいと思っていたんだ」
「世界や地域の平和と安定に貢献している」と言えば聞こえはいいが、沖縄から出撃していった海兵隊員が、ベトナムで、アフガニスタンで、イラクで、実際に現地の住民の命を奪ってきたのだ。基地を提供するということは、アメリカの戦争に加担するという意味も持つ。
沖縄の人々がこれだけ怒りの声をあげていても、また、独立国なのにこれだけ各地に外国軍の基地があっても、多くの国民が「無関心」でいられるのは、これまでに挙げたいくつかの「誤解」に加えて、基地周辺の住民を除けば日々の実生活の中で基地や安保に対してとりたてて不満に感じることがないからだろう。
しかし、この「無関心」が、見えないところで多くの人たちを踏みつけ、傷つけている。今まさに、私たち国民一人ひとりの「品格」が問われているのである。
◆有効な非暴力直接行動
政府が無能にも決断を先送りにし、盲目的に辺野古新基地建設を続行する限り、現場では沖縄県民の抵抗がねばり強く続けられるだろう。
「日本政府が決めたことなんだから、そんなことやっても無駄だよ」と冷笑する人もいるだろうが、けっしてそんなことはない。実は、基地での「非暴力直接行動」は米軍がとても嫌がることなのだ。その具体例を一つ、紹介したい。
米自治領プエルトリコのビエケス島では、2004年5月に米軍射爆演習場が閉鎖・撤去された。
島の面積の3分の2を米軍に強制接収されたビエケス島では、住民は騒音や誤爆、環境汚染などの被害に苦しんできた。1999年に住民が誤爆で死亡すると、溜まりにたまった島民の怒りのマグマが爆発し、基地撤去運動が高揚した。住民たちは、金網を切り裂いて演習場内に立ち入り、テントを持ち込んでキャンプをはった。また、漁船で米艦船が島に入ろうとするのを阻止しようとした。演習場内での座り込みは1年にもわたり、市長を含む100人以上が逮捕されたが、それは住民の怒りにさらに火をつける結果となった。
アメリカは4000万ドルの地域振興策と引き換えに演習場の存続をねらったが、2001年に実施された住民投票で「演習即時中止・基地撤去」が68%を占めたために、演習場の閉鎖・撤去を決断した。
軍事基地は「フェンスの内側」だけでは機能しない。兵士や装備が自由に出入りできるアクセスが保障されている必要があるし、インフラや基地内で必要な労働力を地域社会に依存している場合も多いからだ。

【撮影:初沢亜利】
日本でもベトナム戦争中の1972年、米陸軍が相模原総合補給廠(神奈川県)で修理した戦車を横浜港からベトナムに向けて運び出そうとするのを、市民たちが道路や橋に座り込むなどして阻止したことがある。当時の横浜市長は社会党出身で、市が管理する橋を米軍戦車が通行するのは道路交通法の重量制限違反だとして、市の職員を橋に派遣し、多くの市民と共に通行を阻止した。
このように住民の反感に囲まれた基地は、いざという時に機能しないリスクを抱えることになる。これは、基地としては致命的だ。逆に、基地に対する非暴力直接行動でこうした「リスク」を可視化することが、アメリカに基地の閉鎖・撤去を決断させるファクターになることは、これまでの歴史が示している。
沖縄県民からしてみれば、「これだけ選挙で圧倒的な民意を示したのに、私たちがそこまでしなきゃいけないのか?」と思うだろう。
このままわれわれの政府が暴走を続けるのであれば、本土からも沖縄に足を運び、辺野古で沖縄県民と共に抵抗するのも、また一つの責任のとり方だと思う。