戦後70年の節目となる慰霊の日に、沖縄がどのような社会になっているのか、振り返ってみたいと思う。

Photo by 柴田大輔
クラクションという「地雷」
沖縄を訪れる観光客は、どれだけ道が混雑していても、誰もクラクションを鳴らさないことに気がつくと、「沖縄の人たちはなんて優しいんだ」と感動する。世界中どこの都市でも街の音と言えばクラクション。那覇市は人口あたりの街の騒音が最も低い都市のひとつではないかと思うくらいだ。ところが、沖縄で暮らして何年か経過すると、これはクラクションを「鳴らさない」というよりも、「鳴らせない」状態に近いということを理解しはじめる。
沖縄社会で「加害者」のレッテルを貼られることほど最悪なことはない
車を運転している私が、往来の激しい国道で、違法に右折しようとしている車を見つけてクラクションを鳴らすと、周囲は違法運転している前の車ではなく、一斉に私のことを見る。違法運転している者を咎めるのではなく、それに対して声を上げた者に対して暗黙の批判が向けられるのだ。「今鳴らしたのは誰だ!」という無言のメッセージが私に突き刺さる。この瞬間、私は違法運転に迷惑を被った「被害者」ではなく、クラクションを鳴らした「加害者」なのだ。沖縄社会で「加害者」のレッテルを貼られることほど最悪なことはない。
ある本土人が、沖縄人(ウチナンチュ)の友人を乗せて車を運転したときの話をしてくれた。その本土人が迷惑な車に対し、何気なくクラクションを鳴らしたとき、そのウチナンチュの友人が慌てて「あぃ、いま、なんで鳴らす!」と指摘してきて、その慌てぶりに驚いたのだという。なぜそのウチナンチュが、とても迷惑そうな、居心地の悪そうな態度を取ったのか。それは、自分もクラクションを鳴らす本土人と同じだと周囲から思われてしまうと、「加害者」の共犯とみなされ、さまざまな不都合が生じるからだ。
もし私が毎日クラクションを鳴らしながら生活すれば、プライバシーが事実上存在しない沖縄社会でそのことはやがて周知となり、「樋口さんは怖い人さーねー」という噂、あるいは言葉にならないニュアンスがなんとなく広まっていくだろう。そして、私の商売からお客さんが一人減りまた一人減りして、やがて生活基盤が失われる。
このルールは、本土人の目には見えない地雷(?)のようなもので、「沖縄の空気」を読めずにいると大怪我をする。この原則に抵触する人は、沖縄で長期間存続することができない。ウチナンチュは、「地雷」の怖さをよく理解しているので、それを避けるための直感力が抜群に研ぎすまされている。人の心の変化を敏感に察知することにかけては、ウチナンチュの右に出るものはいないのではないか。彼らに噓は通用しない。

Photo by 初沢亜利
「NO」と言えないウチナンチュ
クラクションを鳴らすことができない沖縄社会では、人と異なる態度を取ることは難しい。人からのちょっとした誘いに対しても、面と向かって断ることはできない。少々大げさに表現すれば、そこには人間関係に対する絶縁状のような感覚が含まれていて、断られた方は「裏切られた」と解釈しかねない。「横のつながり」が緊密な沖縄では、小さなクラクションが思わぬ波及効果を生む。
ある学生が私に自分の体験を語ってくれた。「大学4年生になって将来の事を考えるようになり、少しは勉強する時間を確保しようと思って、いつもは断らない飲み会の誘いを断ったら、別々の友人10人から連絡が来なくなった」という。沖縄のような狭い島社会で、人間関係を分断してしまえば、あっという間に居場所を失ってしまう。

Photo by 初沢亜利
沖縄の学力が「低い」というデータを持ち出して、子供に対して、「なぜもっと勉強しないのか?」と苛立つ大人がいる。しかし、学生にとって「ひとりで勉強する」という単純な行為が、実際にはそれほど単純ではないことを理解しなければ、沖縄では「教育」問題ひとつ解決しない。
本土的な価値観からすると一見些細なこと——例えば、車に乗ってクラクションを鳴らすこと、誘いを断ること、人に反論すること、集団の中で真っ先に意見を述べること、割り込んだ相手にひとこと注意するといったことにも、公然と人間関係にNOを突きつけるニュアンスが含まれていて、これが周囲の人を慌てさせることになるのだ。
沖縄人は、あらゆる手段を用いてNOと言うことを避けようとする
だから沖縄人は、あらゆる手段を用いてNOと言うことを避けようとする。沖縄では相手に直接NOと言うくらいならば、空手形を切ったり、約束をすっぽかしたり、曖昧に引き延ばしたり、返事をしないで放置する方が、人間関係のダメージが少ない。よく沖縄人は「テーゲー(いいかげん)」だと言われるが、そこには一定の沖縄ならではの社会的合理性があるのではないか。テーゲーであることは、本土的な価値観から見ればまったく理解しがたい、無責任な行動に映りがちだ。しかし、この「ダブルスタンダード」が、沖縄社会においては人間関係に不要な摩擦を生まないための、積極的な社会的機能を果たし得るのだ。したがって、社会通念上も、テーゲーであることがおおいに許容される。というより、テーゲーでなければ人間関係がうまくバランスしないところがある。

Photo by 初沢亜利
「個性」を発揮することを拒む沖縄社会
NOと言ってはいけない沖縄社会では、必然的に、自分の意志に反することでも、理不尽なことでも、受け入れなければならない。沖縄には「模合(もあい)」という頼母子講が根強く残っているが、中には「学生時代から30年間続いている」といったものも珍しくない。典型的には月に1回、同級生が経営するレストランに10数名が集まり、食事をしながら毎回変わらず30年前の話をする、というような会だ。それは、単なる親睦のみならず、レストランを経営する同級生への経済援助といった役割も果たしている。そのような模合メンバーのひとりが私に「いつも同じメニューで、正直なところあまり美味しいとも感じない。だから人知れず自宅で食事をしてから参加するんです」と語ってくれたことがある。しかし、だからといって模合から脱会すれば、30年来の友人に対する「裏切り」となり、彼との信頼関係を壊すだけでなく、模合を通じて複雑につながっている無数の人間関係に同様のメッセージを発することになる。この場合もむろん、脱会した方が「加害者」であり、裏切られたレストランオーナーは「被害者」である。

Photo by 初沢亜利
あるいは、沖縄社会の年長(シージャー)主義は絶対で、それがどれだけ理不尽なものでも、親の言うことに背けば、親類縁者全員に対する「裏切り」とみなされることを覚悟しなければならない。長男であればその「罪」は特に重い。男性が優位な沖縄社会の長男は、なにかにつけて優遇されて、甘やかされるが、その一方で一族からがんじがらめにされる。それゆえ彼らは声を上げようにも上げられず、自分らしく生きることが難しくなる。結果として個性を発揮することができず、打たれ弱い。
別の、30年来の模合仲間3人が連れ立って飲んでいたとき、会話に加えてもらったことがある。私が時間をかけて彼らの話に耳を傾けると、やがてその中のひとりの女性が、現在隣人とのトラブルで深刻な悩みを抱えていて、多額の費用をかけてまで引っ越ししようかどうかを思案中だという。隣のアパートに数年前から住んでいる母子家庭で、毎晩のように子供が虐待されているというのだ。アパートの薄い壁は音が筒抜けで、聞いていて辛いし、子供にとっても悪影響だ。私が「通報はされないのですか?」と訊ねると、「自分が通報したことが知られてしまうリスクを考えたら、とても怖くてそんなことはできない」という。
過去30年、毎月顔を合わせて何時間も会話する旧友たちが、お互いのことを本質的な意味で何も知らない
印象的だったのは、この話を聞いていた彼女の30年来の男友達が、「おまえ、こんなふうに考えるヤツだったのか?」「こんな話は、今まで一度も聞いたことがなかった」と驚いていたことだ。この発言を聞いて、私の方が驚いた。過去30年、毎月顔を合わせて何時間も会話する旧友たちが、お互いのことを本質的な意味で何も知らないのだ。逆に考えれば、人間関係を30年間続けるためには、相手に踏み込んではいけないし、人生の重要な悩みに向き合うことも避けなければならないのかもしれない。
私が後日この話を別のウチナンチュにしたら、彼は神妙な顔つきで頷きながらこういった。
「このお話の方々のことがよくわかるような気がします。沖縄では、親密な人間関係を壊すことが絶対にできないので、結局お互いを傷つけない、表面的な付き合いしかできないような気がします。相手に踏み込むのも踏み込まれるのも怖くて、心を開くことが難しい。私たちは、いつも誰かと一緒にいるけれど、実はとても孤独なんです」
不用意に声を上げてしまえば「悪気がなかった」では済まされない。自分が意図していなくても、人の気分を害してしまえば厳しい結果を招く。このため、沖縄社会に生きる人たちは、発言するときに、自分の考えを表明するよりも、他人がどう感じるかについて、慎重に間合いを取る傾向が強い。全国を回って講演をしているあるセミナー講師が、「講演会でも、イベントでも、沖縄は全国的にもっとも笑いやウケを取りにくい地域のひとつだ」と語ったことがあった。それはウチナンチュが感情に乏しいからではなく、周囲から浮き上がることを恐れるからだろう。

Photo by 初沢亜利
また別の学生たちはこんなことも語ってくれた。
「授業で先生に聞きたいことがあっても、ほかの学生から『あいつばかり良いカッコしている』と思われるリスクを考えると、何も言えなくなる」
「バイト先でやりたい仕事があったのだが、『アイツ調子に乗っている』と思われそうで、あまりやりたくない係に手を挙げた」
はっきりとした物言いをする人に対しては、表面上はやんわりながら、あるいは、ほとんど目には見えないほどの微妙さで、その発言を取り消せと言わんばかりの強い圧力がかかる。自分の意見は常に他人の出方を見てから言う。自分の意見が際立つくらいなら、いっそ意見など持たない方がいい。うかつに意見を述べると、クラクションを鳴らして、自分が「加害者」になってしまうかもしれないからだ。

Photo by 初沢亜利
「できるものいじめ」の社会
この社会習慣は、人をいたずらに傷つけることがないという、明らかな利点がある。間違いを犯した人、失敗した人にも居場所を提供し、少なくとも表面上では人を追いつめない。沖縄のご当地ヒーロー・琉神マブヤーは、最後は敵を抹殺するのではなく、赦すところで終わるのもこの美しい文化を象徴している。
このルールは成長しようとする若者から挑戦と成長と失敗の機会を奪う
一方でこのルールは、人がもっとも個性を発揮しづらく、おたがい切磋琢磨できず、この社会で成長しようとする若者から挑戦と成長と失敗の機会を奪うという、重大な弊害を生んでいる。善意を持って注意すること、学生に厳しく叱ること、部下に社会の基本動作を教えること、友人に欠点を指摘すること、将来のために現実的な議論を戦わせることなどの多くは、沖縄では最も困難なことのひとつだ。
少々乱暴な一般化を試みると、本土のいじめは弱いものいじめである。仕事のできないもの、いつまでも学ばないもの、やる気のない者に強い圧力がかかる。これに対して、沖縄のいじめは「できるものいじめ」だ。少し個性的な人物、一所懸命でまわりが見えていない人物、ちょっと生意気なタイプがターゲットになりやすい。
大胆なアイディア、売上を飛躍的に増加させる営業努力、経営を別次元に進めるイノベーションなどは、沖縄のタブーである。周囲が「できない人」だらけであれば、問題は生じない。グループに1人でも「できる人」が加わると、ものごとを変えることになる。これを避けるために、組織内に「できるもの」を排除する圧力がかかる。本土で成功したウチナンチュは少なくないが、その実績が見込まれて沖縄の支社にUターンしてきた優秀な人材が社内で浮きまくり、協力者を獲得できず、短期間で鬱になっていく事例を私は何人も見てきた。
教育の現場では、文章がしっかり書ける学生でも、授業中ほとんど質問が出ない。思考していない訳ではない、意見がない訳でもない、時間をかけて一対一で話せば個性が光る。しかし、周囲の反応を考慮しなければ発言できないため、結果として、議論の機会が失われ、思考と論理が磨かれない。学ぶことの意味が深まらなければ情熱が湧かず、学力は上がらない。

Photo by 初沢亜利
企業の人材育成の現場でも、先輩が後輩を注意できず、人を育てることができない。上司が愛情を持って厳しく注意すると、若者は「いじめられた」という態度を取りがちで、いつのまにか上司である自分が「加害者」にさせられてしまっている。エリート社員ほど叱られず、厳しさを経験せず、十分な実力を身につけることができず、目的を失って離職する。沖縄では、就職後3年以内の離職率がおよそ2人に1人、全国的に圧倒的なトップである。
沖縄は女性登用が遅れていると指摘されているが、そもそも女性が管理職になりたがらない、パートが正社員になりたがらないという傾向がある。責任ある立場におかれて人から目立ってしまったり、これまでの同僚に注意・指摘しなければならない立場に置かれることは、沖縄社会では極めてリスクが高い。これだけ能力のある女性の進出が進まず、正規雇用比率が全国最低である理由は、社会的な要因が大きい。

Photo by 初沢亜利
同様に、沖縄社会でリーダーシップを発揮することは茨の道だ。人をまとめようにも、反応がない。行動を強制すれば人が離れて「加害者」にさせられる。以前私が経営していたホテルの組合委員長は、従業員のためによかれと思って一所懸命努力しても、協力者は少なく、仕事が大量に押し付けられ、感謝もされずに相当傷ついていた。
業界の間でも、例えば社員の給与を業界水準以上に上げるなど、目立つことをすると強力に妨害される。「ひとりだけいいかっこをすると、まわりが迷惑する」という、声なき声だ。
沖縄社会は深刻な人材不足に直面している
ウチナンチュは本当に多才で有能だ。多岐にわたる業界で、沖縄出身者の活躍は目覚ましい。成功するウチナンチュの多くは県外、国外で能力を開花させる。しかし、外で成功したウチナンチュも、沖縄に戻るとつぶされて居場所を失ってしまう。結果として、沖縄社会は深刻な人材不足に直面している。これまで沖縄社会が永きにわたって個性を阻害してきたことの弊害だ。こうしたことを繰り返すことで、沖縄社会はイノベーションを生み出す力をすっかり失ってしまったように見える。世界や日本で通用するオンリーワン企業はほとんど生まれない。産業の生産性が上がらなければ、雇用の質も低下し、十分な収入がなければ県民の生活の質も低下する。結果、数々の社会問題が拡大する。

Photo by 初沢亜利
「オール沖縄」の本質
「物事を変えてはいけない」「新しいものを生み出してはいけない」
つまり、戦後70年間でつくりあげられた沖縄社会の基本的なルールは、「物事を変えてはいけない」ということと、「新しいものを生み出してはいけない」ということだ。この重大なルールは、人間関係のみならず、教育やビジネス、行政、社会運営の基本動作、そして「オール沖縄」の運動にも大きな影響を及ぼしている。それどころか、「オール沖縄」は、この社会規範が動かしていると言っても差し支えないかもしれない。「オール沖縄」を中心とする現在の沖縄の政治的潮流を、このような沖縄の社会的、文化的な背景と重ねて理解すると、意外な側面が見えてくる。
先日、沖縄から放送されたテレビ朝日の「朝まで生テレビ!」(沖縄では琉球朝日放送で放送された)で、パネラーの恵隆之介氏が、稲嶺進名護市長の要望書について指摘していたことが印象的だった。2011年と2013年の2度に渡って、キャンプハンセンの名護市の部分約162ヘクタールについて、返還期限が経過したにもかかわらず、その期限を延長するよう、防衛局に要望書を提出していた件だ。
また、日本記者クラブ沖縄取材団が6月12日に名護市で開いた会見において、稲嶺進名護市長は、「辺野古新基地反対」の立場をとりながら、同時に「日米安保支持」「現状のキャンプシュワブであれば容認」と発言している。
翁長知事も、「辺野古に新基地はつくらせない」と繰り返し発言する一方で、浦添新軍港の開発については2001年那覇市長時代からの計画を推進する立場を変えていない。特に、現在沖縄県知事となった翁長氏は、浦添新軍港開発の当事者である那覇港管理組合のトップを兼任し、同軍港開発の直接の決定権者であるにも関わらず、である。

Photo by PIXTA
「オール沖縄」とは、基地反対運動と言うよりも、壮大な現状維持運動
翁長知事の政策は、辺野古新基地反対であることを除けば、ほとんど前仲井真県政時代と同じだと指摘されている。この現象を素直に解釈すると、「オール沖縄」とは、基地反対運動と言うよりも、壮大な現状維持運動と言うべきではないだろうか。「物事を変えてはいけない」「新しいものを生み出してはいけない」という沖縄社会の重要2大ルールに完全にのっとって政策を進めているように見えるのだ。
翻って考えると、「オール沖縄」は新しいものを生み出す活動ではないように見える。ひとりひとりの個性を尊重して、多様性を受け入れるというよりも、同調圧力で他の意見を許さないという傾向の方が強くないだろうか。
魂を持った人材を沖縄から生み出さなければ、結局どれだけ基地が返ってきても、社会は成り立たない
戦後先人から引き継がれた沖縄社会は、若者の個性を抑圧し、新しいものを生み出すことを避けてきた。私たちは、いまだにその流れを変えることはできないのだろうか。
ひとりひとりの自由な生き方に挑戦すること、勇気を持って自分の声で語ること、異論を恐れずに心を開くこと、人間関係の摩擦を恐れずに信念を貫くこと――私が信じる本来のウチナンチュとは、このような人たちだ。魂を持った人材を沖縄から生み出さなければ、結局どれだけ基地が返ってきても、社会は成り立たない。
終戦の傷跡がまだ残るかつての沖縄で、このようなウチナンチュの魂に触れた岡本太郎は、名著『沖縄文化論』の中で、「沖縄が日本に復帰するのではない、日本が沖縄に復帰するのだ」と表現した。日本が経済大国に突き進む過程で忘れかけている魂が、当時の沖縄にはまだ残っているのだという。日本人が復帰すべき魂がここにあるのだ、と。
慰霊の日に、私たちが成すべき真の鎮魂は、後の世代を引き継ぐ私たちが、自分自身を生きることではないだろうか。

Photo by 初沢亜利






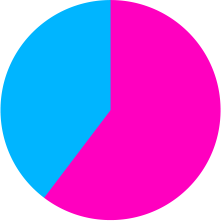






















人気の回答
Invalid date
■