1996年のSACO合意、ならびに翌年の1997年に名護市辺野古への米軍普天間基地移設案が名護市民投票において反対票が優勢であったにもかかわらず比嘉鉄也元名護市長によって正式に受け入れを表明されてから18年。2004年の最初のボーリング調査に政府が着手してから11年。そして2014年の実質的な移設工事開始から1年。その間さまざまな案が現れては消え、状況が変化するごとに問題が起こり、140万余の人口を抱えるこの小さな島は翻弄され続けた。18年という長い年月は、一地方都市を疲弊させるには十分な時間に思える。だが、太平洋地域の安全保障を左右するはずの基地問題は、オキナワにその大部分を押し付けたまま解決の糸口すらつかめていないように見える。

Photo by 初沢亜利
今、沖縄県民はかつてない混乱の渦中にある。島の現状をこう表現すると、「何を今さら。これまでだってずっとそうだったじゃないか」という怒気をはらんだ声が聞こえてきそうだ。あるいは、「負の歴史を軽んじるな」とのお叱りを受けるだろうか。

Photo by 初沢亜利
昨年のちょうど梅雨が明けようかというころ、沖縄県内では「明日にでも移設工事が着工するのではないか」との情報が流れ、連日緊張が走っていた。そして7月1日、政府はキャンプ・シュワブの砂浜部分にある既存施設を解体し、辺野古沖に普天間の基地機能を強化した新基地を建設する工事へ本格的に着手した。同年11月に翁長雄志現沖縄県知事が前職を破り当選した直後、ぼくは気の置けない同級生の集まる飲み会で、こう聞いてみた。
「知事選の結果についてどう思うか」
「今の沖縄についてどう感じているのか」
「辺野古移設をどう思うか」
集まっていたのは、みな基地問題がそれほど身近ではない那覇市や、その近郊で生まれ育った者ばかりだ。

Photo by 初沢亜利
ぼくは、あえて軽口をたたくように、冗談めかした口調で問いを投げた。かなりシリアスになりつつある基地問題について、みんなの前で話すのが難しいことは理解できるからだ。だが、ぼくの予想に反して、彼らの口からは意外なほど様々な意見が飛び出した。もちろん議論の中では、翁長新知事への思いや、基地移設に対する賛成・反対それぞれの意見が交錯した。しかし、内容はともあれ、20年以上の付き合いになる彼らが、これだけ当事者としての意識を持つに至っていることに驚いた。聞けばみな、これまで具体的に基地問題に言及することはなく、例えば2012年に普天間基地へオスプレイが配備されたときなども、仲間内でその話題に触れることはなかったという。これまで積極的に集会などに参加する友人がいても、どちらかというと、やや冷ややかな目線で眺めていたそうだ。その「空気」は、ぼくにもよくわかる。

Photo by 初沢亜利
以前と比べればかなり薄れてきたものの、沖縄の社会では、地縁・血縁が非常に強い影響力を持つ。それゆえに、沖縄では個人の考えの違いが対立を生むようなテーマ(その多くが基地問題に由来する)について語ることは避けられてきた。
口をつぐんできた多くの県民が県知事選以前と比べて明らかに言葉を発するようになっている
その沖縄で今、これまで分断や孤立を恐れて口をつぐんできた多くの県民が県知事選以前と比べて明らかに言葉を発するようになっている。(失礼を承知でいうが)政治的な話題にまったく興味がないかのように思われた友人が、SNSなどで意外な記事をシェアしているのを目にする機会も増えた。だがそうした行いは同時に、この狭い地域社会の中では生きづらさを背負ってしまうリスクをともなう。

Photo by 初沢亜利
「無関心」ではなく、むしろ強い関心があるからこそ黙ってしまう
ぼくが、ぼくの周りを少し見渡すだけでも、これまで声を上げなかった人が声を上げるようになり、同時にそうした空気に少し怯えるように過剰反応する人が生まれている。そして、その空気が、いまや沖縄全体を包み込むように広がっているように感じる地元の人間が増えている。
もちろん、依然無言を貫く人々も多い。だが「無言」を「無関心」だとみなすのも、少々乱暴な話ではないか。ぼくは今、「無言」の裏に隠れているものが、「無関心」ではなく、むしろ強い関心があるからこそ黙ってしまう現状もあると、強く感じているからだ。

Photo by 初沢亜利
沖縄の生年祝い、73歳のトゥシビーを迎える県内有名企業役員の知人は、これまでの半生のほとんどを保守として生き、社を挙げて自民党を支えてきた。そうすることで県内の業界を盛り立ててきたという誇りを持つその彼が、前回の知事選では翁長氏に票を投じたという。「さすがにこれ以上ウチナーンチュが馬鹿にされるのは我慢できなかった」と笑いながら話す彼は、知事選前に勤務先の会長に投票先を明かした。「今の自分があるのは会社のお陰なのだから、こそこそ投票するのは仁義にもとる」と考えた末の選択だったそうだ。
「同じような思いを抱き、それが投票行動に結び付いたという話は何名もの経済界の知人から聞いている。それを明らかにできないことに悔しさを感じてもいる。そこに自分とそう大きな差はないはずだ」
仲井真前知事の辺野古移設受け入れ表明から始まった一連の混乱が沖縄の人々に変化をもたらした
役員としての立場を超えて自我を貫き、そのうえで所属先への筋も通そうとした彼の行動は美談にも思える。その話を聞いたとき、ぼくは個人の意思表明をするために、わざわざそんな特殊なプロセスを経ないといけないことに若干の違和感を感じつつも、称賛の言葉を並べた。だがそれは、われわれが「社会と個」を天秤にかけたうえでその思いを踏み絵にし、そうした風変わりなプロセスを経ないと何かを行動に移せないほど、負担を強いられていることの現れではないか。いずれにせよ、仲井真前知事の辺野古移設受け入れ表明から始まった一連の混乱が、沖縄の人々に変化をもたらしたのだ。

Photo by 初沢亜利
戦後沖縄にとって「反対すること」が目的化したように見えた基地反対運動もここのところ勢いづいてきている。沖縄のメディアは連日トップで辺野古移設問題を報じ、目下世間をにぎわせている安保法制論議とも相まって、少なくとも本土復帰後世代のぼくの記憶にはないほどの熱を帯びていると言っても過言ではない。身内の話で恐縮だが、これまでそういった類にほとんど言及することがなかったぼくの母親も、夕方のローカルニュースを食い入るように凝視し、夕食時には家族に向かって「また辺野古の工事が再開したらしい。絶対に許しちゃいけないよ」などと語るのだ。活動家ではない市井の人のそうした姿を目の当たりにすると、あらためて基地問題が動き始めたことを実感する。
今の「オール沖縄」には、選挙に勝った側の「私たちの正しさ」のようなものが根底にある
基地問題が熱を帯びるのとともに、「オール沖縄」という言葉が再び市民権を得ていったようにも思う。しかし「オール沖縄」とはもともと、2012年の普天間基地へのオスプレイ配備の際に、県内の保革が一致し、共闘したことに由来する。その時点では辺野古移設に対し、自民党を含めた各党が反対していたがために、この言葉は成立していた。だがその後、自民県連が移設容認に転じたことにより、そもそもの背景は一度失われている。前回の知事選では、確かに保守陣営が割れて、自民を離党した一部がいわゆる革新勢力と結びついたものの、言うまでもなく仲井真陣営も少なくない票を獲得したし、事前の予想よりも翁長氏の票は伸びなかったと見る向きもある。投票率がそれほど高いものにはならなかったのも事実だ。「オール沖縄」という言葉が移設に反対する人々の集合体を指すのならば、そこに加わることのできない人々が、翁長氏が獲得できなかった票の数だけいることになる。転じて今の「オール沖縄」には、その状態でありたい、あるべきだとの希望や願望、それに加えてもしかすると選挙に勝った側の「私たちの正しさ」のようなものが、その根底にあるように感じられる。

Photo by 初沢亜利
このテーマに触れることについてはぼくも及び腰になる。だから、言い訳のように記しておくと、ぼくは辺野古移設などもってのほかだし、こんな理不尽は絶対に認めるべきではないという立場だ。この件に関して地元・辺野古や沖縄県が強硬な姿勢で突っぱねるのも当然だと思っている。それでもぼくが、あらためて問題提起したいと思ったのは、今の沖縄県内の言論状況に不満めいた感情を持っているからである。ぼくは、移設阻止の先にこの島の将来像を見出そうとするならなおのこと、手を取りあい協力するため、今は「オール沖縄に自分が含まれないと思っている層」との分断を避け、より慎重になるべきではないかとすら思っている。

Photo by 初沢亜利
「オール沖縄」で切り捨てられるものについてのリスクは、翁長知事がよく口にする「ウチナーンチュのアイデンティティ」とともに知事選前から語られていた。この言葉に違和感や嫌悪を表明する声も少なくない。
「オール沖縄」という言葉を触媒にして県民の一体感を強調すればするほど、むしろその輪に加わることのできない人たちの反発が強まっていく
ぼくがこの原稿の前半部分ほとんどを割いて強調したかったように、現在の沖縄はかつてない混乱を抱えている。その混乱の度合いの深さだけ慎重にならなければいけないというのは先に述べたとおりだ。だが現状は、「オール沖縄」という言葉を触媒にして県民の一体感を強調すればするほど、むしろその輪に加わることのできない人たちの反発が強まっていく構図にある。那覇市近郊自治体のある市議は、ブログやFacebookを通して、日常的に翁長県政や県内新聞2紙への批判を繰り返している。彼の主張をつぶさに見ていくと、いわゆる「ネトウヨ」と呼ばれる人たちのような極端な主張や揚げ足取りのような批判をしているわけではないが、中には「批判のための批判」のような、少し無理があるのではと思わざるを得ない意見も散見される。その文中に時折垣間見えるのが「オール沖縄」という言葉への嫌悪感だ。知人を介して、彼の人となりや評判もそれなりに耳にしているが、普段の言動や行動から察するに、県政やマスコミをハナから敵だと認定しているような姿勢は、ある種の「感情のもつれ」が原因だろうと想像できる。そしてそれは、何もその市議に限ったことではない。多種多様かつ解決が困難な社会問題が山積する中、基地問題が「極端に」取り上げられ続けることに「疲れた」ようなことを口にする県民が増えたように思う。

Photo by 初沢亜利
「意見を異にするものに対しての排除」をはらんでいるようであってはならない
おそらくまだまだ長く続いていくであろう基地問題については、「誰かのもの」にするのではなく、立場の違いを認めたうえでの真の意味での「オール沖縄」で向き合っていくことが望ましいはずだ。ましてや本来、多様な意見がありながらもそれを受け入れ、共にする理想を目指していくときに包み込んでくれるはずだった言葉が、ただの単語と見過ごすのは危険と思えるほどに、「意見を異にするものに対しての排除」をはらんでいるようであってはならないとぼくは感じる。
沖縄の文化は「チャンプルー(混ぜこぜ)文化」と呼ばれ、あらゆるものを取り入れ、消化して、自分たちの血であり肉にしてきた。基地さえも、言ってしまえばそうだ。一筋縄ではいかないが、その文化があるからこそ、ぼくはこの場所に生まれたことを誇りに思う。
だが最近は、愛すべきその文化を信じ切れない自分もいる。
かつてこの島では「オール沖縄」という便利な言葉を作らなければ、分断を乗り越えて手を取り合うことができなかった
沖縄は、誰かを排除することなく、分断することなく、違う話をしている隣の人の声に耳を傾けることができる文化的な土壌を持っているはすだ。もしそれができないのであれば、この小さな島の将来の見通しは絶望的に暗いと言わざるを得ないのではないだろうか。かつてこの島では「オール沖縄」という便利な言葉を作らなければ、分断を乗り越えて手を取り合うことができなかった。しかし今ぼくたちは、「オール沖縄」ではなく「沖縄」そのものを受け止め、許し、慈しみ、その未来を育まなければいけないのだ。かつてないほどに「沖縄」に目が注がれている今だからこそ、できることがある。沖縄の人々の意識が変わりつつあることを、日本中に知らしめたい。

Photo by 初沢亜利





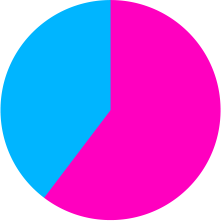






















人気の回答
Invalid date
■