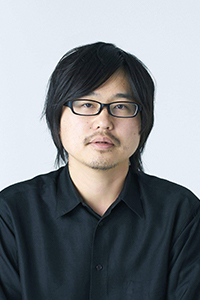今年も、3月11日がやってきた。震災から8年が過ぎたことになる。
8年という時間は、長いとも短いとも言える。8年かけてようやく日常が戻ってきたという声もあれば、山積みになっている未解決な問題を処理するためには、まだまだ時間が必要だという声もある。それらはどちらも真実だろう。
ひとつだけはっきりしているのは、ぼくたちは年々、震災について語らなくなっている、ということだ。これは美術の世界でも同じで、美術館での企画展やコンペ、美大芸大の卒業制作展でも、震災をテーマにした作品は、年々少なくなってきている。これは首都圏だけに観測される事象ではなく、東北での展覧会や卒業制作展も、概ね同じような傾向にある。
8年経って、徐々に震災の傷が癒えてきたのだ、と捉えることもできるだろう。たしかに、心の傷が癒えるためには、適度な「忘却」が必要である。震災の傷を片時も忘れることなく、常にトラウマティックな苦しみに苛まれる状態を脱したという意味では、肯定的に考えるべきなのかもしれない。
しかし、明らかに経済的なカンフル剤でしかない東京オリンピックと大阪万博へ向けた空疎な狂想曲に、震災への問いや被災地の声がかき消されている現状を見ると、不自然なくらい、積極的に忘却しようとしているのではないか、という疑問がふつふつと湧いてくるのである。
昨年、都内のある著名な美術館で、世界中の「大惨事」をテーマにした大規模な美術展が開催された。その展覧会に出品していた、ある若手の日本人作家が、東日本大震災の原発事故をテーマにした作品を出品していたのだが、その作品を見て、ぼくは目を疑った。その作品は、防護服を着た原発作業員の肖像画を描き、彼らの命が、刻一刻と死へ近づいていることを暗示するインスタレーションだったのだ。複数描かれていたその原発作業員の肖像画には、特定のモデルがいるのかどうかも明示されず、作者がどこに、どの程度取材をしたのかも不明であった。これでは、現代美術を悪用した「デマ」ではないか。
さらに驚き、そして暗澹とした気持ちになったのは、この作品がキュレーターによって選ばれ、何の問題もなく美術館に展示された挙げ句、展覧会開催中も、特にその倫理的、道徳的問題を指摘されることがなかった、という事実である。現代美術にとって、東日本大震災や原発事故はもう、数ある「大惨事」モチーフの内のひとつでしかなく、自分たちの人生や生活と結びつく問題ではなくなってしまったのだ。
もうひとつ取り上げたいのは、2018年8月3日にJR福島駅前に設置された、ヤノベケンジのモニュメント《サン・チャイルド》が、防護服やガイガーカウンターを身に着けたその姿から「原発事故の風評被害を増幅するのではないか」といった批判を受け、撤去された事件である。先の原発作業員の作品とは反対に、《サン・チャイルド》の事件では、設置からわずか7日後に、批判を受けたことに対するヤノベ本人の謝罪が発表され、8月28日には木幡市長が撤去の方針を示し、9月20日には撤去が完了していた。
震災の「モニュメント」をいかに残すか、という問題は、未だに十分な議論もなされぬまま、放置され続けている。《サン・チャイルド》の件は決して例外ではなく、震災に関する現代美術で、モニュメントや記念館のような公共空間に開かれたものが、市民の理解を得た上で作られた例はきわめて少ない。限られた「アートピープル」だけが訪れる美術館やギャラリーとは違い、公共空間を占拠するモニュメントは、否応なしに人々の視界に入り込み、時には忌まわしい記憶を呼び起こしてしまう。
《サン・チャイルド》の件に関してぼくは、ヤノベに対して同情的ではあるものの、問題が無かったとは思わない。そもそも、撤去された《サン・チャイルド》は過去作品であり、この場所に設置することを想定して作られたものではなかった。福島駅前に、しかも恒久設置するモニュメントとして、本当にこの造形で良かったのかどうか、きちんと議論し、試行錯誤する時間と労力は割くべきだったし、それをスキップして設置を決めた市長とヤノベの判断は、やはり軽率だったと言わざるを得ない。
だからこそ、批判を受けたからといって迅速に、いかにも「ネット炎上対策」のように、すべてを白紙に戻してしまったことが残念でならない。もし、批判を受けて《サン・チャイルド》を作り直すことができたなら、あるいは、この場所に設置するための新作を作ることができたなら、震災をモチーフとしたモニュメントが、どのようなかたちであれば受け入れられるのかという議論が起こり、新たなモニュメントを作るために、作家がチャレンジする機会が生まれていたかもしれないのだから。(※1)
優れた美術作品は、作品の内に込められたコンセプトやメッセージとともに、長い時間を生きる。それは、ぼくたちのような生身の人間が宿命的に持っている「忘れっぽさ」に抗うための、きわめて具体的なツールである。だからこそ、美術作品は、思い出したくないもの、忘れたいものを、強制的に突きつける暴力装置にもなり得る。その2つの側面は、どちらも美術作品が持つ力なのだ。
おそらくぼくたちは、震災を扱った美術が、どのようなバランスでその2つの力を持ち合わせるべきなのか、まだ納得できる答えを手にしていない。もしかしたら、太平洋戦争に対しても、戦後に数多く起こった公害問題に対しても、阪神・淡路大震災や地下鉄サリン事件に対しても、美術がどのように忘却に抗いつつ、同時に暴力装置であることを許容できるのか、結論が出ないまま、今まで生きてきたのかもしれない。
ぼくは、震災後を生きる美術家、美術批評家として、そのような問題への自分なりの答えを出すために活動を続けてきたつもりだ。震災後から現在まで、ぼくは、アーティストたちとともに福島でも東京でも、震災をテーマにした作品を発表し続けているが、ここでそれらの詳細を書くことはしない。そのかわり、ぼくが震災と美術について考える時、いつも頭の中に浮かんでくる文章を引用したいと思う。それは、1997年に、阪神・淡路大震災後の神戸の街を歩いた村上春樹のエッセイの一節である。村上は、震災から2年が経ち、表向きは「復興」したかのように見える街並みの中に、それでも消し去ることのできない「暴力」を感じ取りながら、次のように書いている。
その平和な風景の中には、暴力の残響のようなものが否定しがたくある。僕にはそのように感じられる。その暴力性の一部は僕らの足下に潜んでいるし、べつの一部は僕ら自身の内側に潜んでいる。ひとつは、もうひとつのメタファーでもある。あるいは、それらは互いに交換可能なものである。彼らは同じ夢を見る一対の獣のように、そこに眠っているのだ。
(村上春樹「神戸まで歩く」『辺境・近境』新潮文庫、1998年、280p)
村上がここで「暴力」を強調しているのは、阪神・淡路大震災という天災だけではなく、地下鉄サリン事件という「人災」についても、同時に考えていたからだろう。ぼくはこの村上の文章が、災害のモニュメントについて書かれたものであると思えてならない。災害を忘れない、ということは、常に「暴力の残響」を聞くことである。しかしそれは、今まさにぼくたちを傷つけようとする暴力ではない。それは、今はまだ、眠っているのである。災害のモニュメントとは、今はまだ眠っている「獣」の片割れのようなものだ。
たとえばぼくたちは、3月11日のような日に、その眠っている獣を、わざわざ見に行く。そして、眠っている獣を見ながら、自分の内側にいるもう一匹の獣が、ゆっくりと目を覚まし、起き上がるのを感じるのだ。いつかまた、この眼前の獣が目を覚まし、起き上がることを想像しながら。
※1 《サン・チャイルド》の件について、もっとも迅速に、かつ真摯な問題提起をしたのは、彫刻家である小田原のどかだった。しかし、彼女の記事が公開された時にはすでに作品撤去は完了しており、その迅速な「炎上対策」によって、《サン・チャイルド》をめぐる話題自体が収束していった。