『月刊 復興人』は、仙台市が震災復興に取り組む地元企業に向けて創刊した無料の雑誌である。その目的は、被災した事業者に取り組む企業に、助成金や貸付金などの公的な支援制度を知ってもらい、事業再開を支援することにあった。2011年10月25日に創刊後、復興に立ち向かう「人」に焦点を当てて取材し、2015年3月まで3年半の間、全42号にわたって発行を続けた。
震災前、私は仙台を中心にカメラマンとして働いていた。震災後、しばらくはあちこちで力仕事を手伝う毎日だった。被災現場で写真を撮るような心境でもなかったし、1年くらいは地元の版元が動くこともないだろうと思っていた。そうしているうちに仙台市から「雑誌を立ち上げるのでスタッフになってほしい」と声を掛けられ、協力することになった。
活動の拠点は、仙台市がクリエイティブ産業の集積を進める、若林区六丁の目地区。2011年の9月から活動を開始した編集部は、ライター3人とカメラマン1人でスタートした。少人数だからこそ意志が統一でき、敏速に動くことができた。『月刊 復興人』の誌面は、仙台圏の事業者向けの復興支援情報を、漫画やイラストを使って利用者目線でわかりやすく紹介した記事とともに、実際に支援制度を使って事業を再開した企業人や、震災後に始動した復興支援プロジェクトなどを紹介する記事で構成していた。
毎月25日発行で、発行部数は約1万部。私は編集部員として、仙台圏を中心に500社を超える企業で話を聞いて回った。

メディアでは、復興に対して前向きな話、とりわけ既に成功が見込める事業が取り上げられがちだが、実際に足で取材した先では暗い話もたくさん聞いた――いや、正直に言えば暗い話のほうがずっと多かった。
宮城県に限らず、津波の被害をモロに受けた沿岸部では、工場を再建しても人がいない。もちろん、住む家がなくなったり、仕事を失ったり、大切な人を亡くしたりといったことで、もう帰ってきたくないという人たちがいる。しかし、そういった事情がなくても、もともとその地域から離れたかった人たちというのもいて、そういう「表」には出てこない気持ちを垣間見ることもあった。
それでも、震災を機にチャンスをつかもうとする企業もある。
私が見聞きした、主に宮城県内の被災企業の「いま」と「これから」について紹介したい。
企業の「復興」は、3つの段階を経る
(1)事業再開への<復旧>の段階
まず、海水に浸かった施設や機械を修理し、必要なものを新たに買いそろえていく<復旧>の段階をクリアしなければならない。沿岸部で甚大な津波の被害を受け体力を奪われた企業は、この時点で資金繰りと人材の確保にかなり苦労する。震災後、自治体から人口が流出し、それまで家事の合間に手伝ってくれていた主婦たちがいなくなり、アルバイトを雇おうとしても都市部に比べ時給が安いため、人が集まらない。人口減少は、震災前から地域が抱えていた問題でもあった。資金繰りについては、国の予算で中小企業向けのグループ補助金などがあったが、提出書類が煩雑すぎて会計士のような専門家を雇わなければ到底書けない。
5年の間に、沿岸部の中小企業の復興がうまくいった事例はあまり聞けなかった
このような理由からか、5年の間に、沿岸部の中小企業の復興がうまくいった事例はあまり聞けなかった。今後は利子補給制度が次々と期限切れになるため、二重ローン、三重ローンを借りて事業を存続している中小企業の体力がどこまで持つのかが懸念される。これが沿岸部の現実だ。
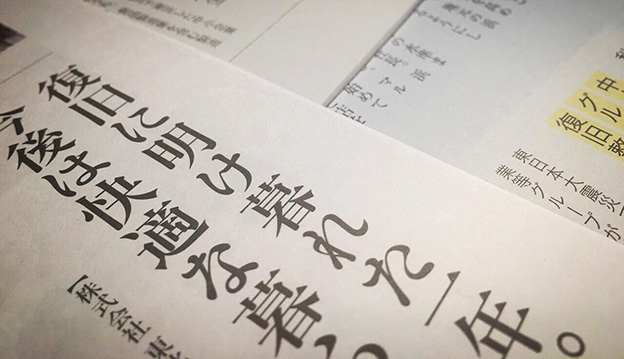
(2)<販路>を確保する段階
事業が再開できたら、次の課題は<販路>の確保である。元の販路を10とすると、成功している企業で7割、平均すると3~4割までしか戻っていないというのが、これまで取材を続けてきた中での実感である。生産活動を始めても、売り先がないと事業を続けられない。運転資金を確保するのも大変だが、取引先のうち1社でも2社でも「事業を再開したらまた商品を置く」と言ってくれることのほうが、企業にとっては励みになる。しかし、事業再開までに時間が経てば経つほど、取引先は離れ、販路の確保は厳しくなる。

(3)新しい事業の<展開>を模索する段階
<販路>の壁にぶつかった企業にもチャンスはある。それは既存の事業を見直し、新しい事業を<展開>することだ。例えば、自社の強みを見直して新商品を作るとか、海外に販路を広げるといったことで活路を見出すのである。5年以内に事業再開にこぎつけた多くの企業がこのやり方で新たな可能性を模索している。外部からのサポートとしては、JETRO(日本貿易振興機構)は早い段階から被災地に入って、海外で商談会を実施する方法や、実際の売り方についてアドバイスしてきた。地元の大学の研究室も、新たな商品開発の手助けをしていて、少しずつ成果が出始めている。
「元に戻す」発想ではなく、新たな事業展開に挑戦している企業がうまくいっている
これまで、特に地元で何代も続いてきたような老舗の場合はその伝統に縛られ、若い世代が自由に事業を展開することができなかった。そうした企業においては、震災を逆手に取り、ゼロから新しいことにチャレンジできるので、張り切っている社長も多い。結果が出るのはまだこれからだが、ここで踏ん張って新たな事業展開に成功できれば、むしろ震災前よりも優れた企業として地域の復興をリードすることも可能だろう。被災地域では、失ったものを完全に「元に戻す」発想ではなく、一度それまでやってきた事業内容を見つめ直し、的を絞って新たな事業展開に挑戦している企業がうまくいっている。
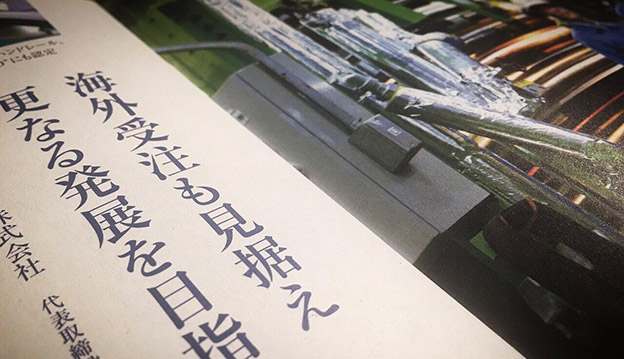
一つ、印象的な事業展開の例を挙げる。若林区にある弘進ゴムという作業靴のメーカーだ。震災後、これまでと同じことをやっていては販路が広がらないといって、摩擦学の世界的権威である東北大学の堀切川一男教授と組んで、「水や油で濡れた床でも滑りにくい長靴」を開発した。厨房や危険な作業現場で便利だと話題になったが、意外なことにフィンランドなどの北欧の雪国で「氷の上で滑りにくい」と売れ始めている。
「Dr.ホッキー」こと堀切川教授は、震災後、とにかく地元の人が集まる居酒屋に通って御用聞きをして、企業のニーズを1つ1つ拾っていった。他にも多くの中小企業と組んで商品開発を手掛けており、そのバイタリティーと地元企業の復興にかける思いに、話を聞くたびに圧倒される。最近は福島を中心に活動している彼が、地域に根差した産学連携の新しいモデルを今後も数多く生み出してくれると想像すると頼もしい。
復興の鍵を握る「行政のジレンマ」
行政の制度を紹介する雑誌を作りながら、行政側の課題も多いと感じていた。たとえ、現場に熱意のある担当者がいて復興をサポートしていても、2~3年で異動になってしまうため、息の長い支援につながらない。また、「相談窓口に来てください」といっても、商品を並べて待っているだけではなかなか人は来ない。
そんな中、仙台市役所農林部に5年間開設された東部農業復興室の活動は有益だった。
県内沿岸部では、田畑に甚大な被害を受けた農業従事者が岐路に立たされていたが、個人事業主がほとんどの農家はそのままでは援助を受けられない。また、農業従事者の高齢化が進んでいて、被災を機に農業をやめてしまう人も多かった。そこで何軒かの農地をまとめて共同で会社を作って、震災後も農業を続けるサポートをしていたのが東部農業復興室の面々だった。彼らは地域の農家の会合に入っていって、リーダーの話を直に聞き、肩をたたきながらまとまっていくというやり方をとった。会社の設立や区画整理、共同で機械を購入するために助成を受ける際に、農家の側に立ってきめ細かいフォローをし、地場農業の存続に貢献していた。
結局、事業者の役に立ったのは、「地元の人たちの中に入り込んでいく」支援だった
結局、事業者の役に立ったのは、「地元の人たちの中に入り込んでいく」支援だった。堀切川教授や東部農業復興室のように、「中小企業を技術で元気にしたい」「農業を続けてほしい」という強い思いを持つ人たちが、行政や大学、民間の枠を超えて、前に進むことを可能にした。非常時に、肩書や身分の枠をいかに取り払って共通の目的を持てるかどうか――それが復興の進展を左右する。
強い気持ちこそが東北の企業のこれからを創る
最後に、最近取材して印象に残っている企業の話で終えたい。
石巻市北上町十三浜では、昔から希少で味のいいベッコウシジミが取れる。東日本大震災が起こった2011年3月11日のあの日、この地でシジミ漁を手掛ける北上川企業組合が結成されるはずだった。
しかし、地震によって引き起こされた津波は北上川を約50キロメートルも遡上。シジミは壊滅状態となった。幸い、代表の佐藤太己男さんをはじめ6人の組合員は全員無事だったが、船も器具も失い、事業を再開する目途が立たなかった。
彼らは運転資金を稼ぐために「福島に行くぞ!」と言って除染作業に従事した。そうして貯めた300万円で手に入れた稚貝を石巻市の北上川に放流し、去年の夏から漁を再開したという。
もう一回金貯めてまたやり直せばいいのさ
結構年のいった漁師さんたちが、「もう一回金貯めて、またやり直せばいいのさ」と明るく言ってのけるのだ。そのガッツと前向きさに、話を聞きながら何度も驚いた。
十三浜は地盤沈下が起きて、北上川河口の中州が水深の浅い砂地となり、以前よりシジミ生産に適した環境となったことが後にわかる。困難に立ち向かった彼らの事業の将来に、明るい光が射している。
もう一度、やってやる――そうした強い気持ちで手腕を発揮している経営者は確かにいる。彼らの多くは、売り上げこそまだ戻っていないものの、震災前とは違うビジョンを描いている。
そして彼らこそが、東北の企業の「これから」を創っていくのだ。

Photo by 三上和仁








