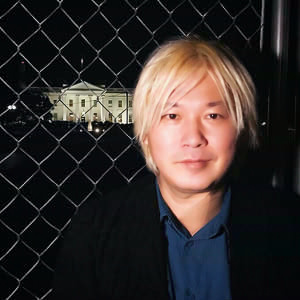フィンランドのオルキルオト島に建設されつつある原発から出た高レベル放射性廃棄物の最終処分施設「オンカロ」。放射性廃棄物を地層処分し、10万年間保持するように設計されたこの施設は、廃棄物が一定量に達すると施設は封鎖され、二度と開けられることはありません。しかし、10万年という想像を絶する未来に暮らす人々に、その危険性を確実に伝える方法はあるのか——この問題を追ったドキュメンタリー映画が『100,000年後の安全』(2009年)です。今回の都知事選の争点の1つとして「脱原発」が急浮上してきた背景には、小泉元首相が脱原発に「転向」したことがあります。実はそのそのきっかけとなったのがこの映画なのです。同映画を配給したアップリンクの浅井隆社長は、2月10日正午までの期間限定で同映画をYouTubeで無料配信しています。無料配信を決断した理由は本サイトに寄稿されている原稿で読むことができます。
僕のメルマガで2011年に映画のDVDが発売された当時、来日中のマイケル・マドセン監督にインタビューをする機会に恵まれました。本サイトに同記事を再掲載いたしますので、放射性廃棄物の問題や都知事選の脱原発争点化についてじっくり考えたい方はぜひご一読いただければ幸いです。
津田:監督が撮影したドキュメンタリー映画『100,000年後の安全』を拝見しました。最初はテーマがテーマなので、「反原発」的なイデオロギー色が強い映画かと思っていたのですが、最後まで観てみると、むしろ10万年後の人類に対し、我々がどのように責務を果たすべきかを問いかけるような重い内容でした。
マドセン:お説教のような映画は避けたかったんです。
津田:監督は元々、コンセプチュアル・アーティストとして活動されていますよね。その立場からストレートなドキュメンタリーを撮っているスタンスが面白いと思います。この映画では冒頭からクラフトワークが映画の中に組み込まれていて、ある種非常にベタな表現ながらも、演出としては非常に効果的だと思いました。個人的に音楽は映像よりも抽象度が高い表現だと思っています。曖昧だけど想像の余地が残されている、というか。監督は「音楽」と「映像」どちらの表現スタイルも手がけていますが、両者にはどのような違いがあると認識されていますか?
マドセン:音楽には芸術の一つの形態として興味を持っています。ドキュメンタリーの多くは、どちらかと言うと「こうあるべき」という意見が全面に押し出されていて、原理主義的だと思うんです。でも先ほども申し上げたように、私はこの映画をお説教のようにしたくなかった。私が音楽が好きなのは、抽象的だからなんですね。この映画でも抽象的な部分を残したかった。そうすることで、観る人は時には希望を抱いたり、時には恐れたりと、自由に想像を育むことができると思うので。
津田:音楽のプロモーションビデオ(PV)のような長回しで撮った映像がところどころに使われている理由も、想像の余地を残すための演出ということでしょうか?
マドセン:私自身はこの映画で撮った「オンカロ」という放射性廃棄物の最終処分場を一つの「現象」として捉えています。今まで永遠に残そうとして作られたのは、ピラミッドや大聖堂など、宗教的な考えに基づいて作られた建築物だけでした。一方、オンカロは10万年後??私は「ポストヒューマン」という言い方をしましたが、人類が存在しなくなったその先まで存在するかもしれないものです。こんな建造物はいまだかつてなかった。まったく新しいものなんです。ですのでカメラワークでも、建物そのものの存在に焦点を合わせるようにしました。これを一つの現象として捉える必要があったからです。カメラクルーには「SFを撮るようなカメラワークを」と指示しました。彼らが未来からのビジターで、現代を何も知らないとしますね。そうすると、たとえばこの部屋に入ってきたとしても何が大事かわからなくて、こうして対談している私たちではなく、電灯のほうが面白くてそちらを撮影してしまうかもしれない。そういう感覚を通して施設のすべてを語りたいと思ったんです。「外部から来て何もわからない」というエイリアン的な視点を保ちながら、真実を見つめていきたかった。
そして「10万年」の問題ですね。果たして人間にとって「10万年」という年月は理解できるものなのか。これだけ長い時間持つ建物を建てることそのものが一体何を意味するのか。映画の最後で私は「これはあくまでも真実であるが、同時に私の視野に映ったものにすぎない」と書きました。私が撮ったのは実在する場所、リアルな人たちです。けれどもそれは、どこかあの世のような異世界につながっている、そういった感じを私は受けました。ある意味では「詩的な真実」と言えるかもしれません。
そして私自身はカメラを長回ししているのですけど、これはある意味で「遠近法」に似ています。どこかに焦点を合わせつつ遠近法も取り入れることによって、何を語ろうとしているか、どこを見つめているか、それが明確になるようにと考えて取り入れました。
現在のような遠近法が確立されたルネサンス期には、神の作りたまいし存在だった人間の生物としての側面が浮き彫りになり、それが科学の登場につながりました。人体の解剖なんて、それまでは「神への冒涜」とされていた。でも科学の登場によって人間は解放され、万物に含まれる真実をつまびらかにしていこうとします。
私はこれをサウンドでも表しています。最後に使った音楽はクラフトワークなどにも影響を与えている先駆的な作曲家エドガー・ヴァレーズとアルヴォ・ペルトの曲です。つまり「何かの夜明け」を思わせる音楽を使っているんです。
アートは時を超えて存在し得ます。この映画は事実を切り取るドキュメンタリーでありながら、アートでもある。それは観る人にさらなる解釈の余地を与える、あるいはレベルの高い質問を発するにも等しいことなのではないかと思っています。
津田:あえてジャーナリズム的な視点で語りますが、この映画は「原発の是非という問題とは別に放射性廃棄物の問題は存在する」という事実をくっきりと浮かび上がらせたところに大きな意義があると思います。「10万年」というキーワードを軸にインタビューをしていくというアイデアは始めからあったのでしょうか。それとも制作していく中で生まれてきたものなのでしょうか。
マドセン:最初からこのスタイルで行きたいと思っていました。私がもっとも大事にしていたのは「10万年」というタイムスパンと現場にいる人たちとのコミュニケーションです。オンカロに初めて行った時、そこで作業していた人たちに「完全に理解するのは難しいかもしれないけれど、原発の是非ではなく、『10万年』という年月の持つ意味が知りたい」とはっきり申し上げましたね。撮影を始めて2、3日経った時、私は安全委員会の方がこう言ったのを聞いて驚いたんです。「オンカロの存在は忘れてもらったほうがいい、そのほうが安全だ」と。なぜか。その人いわく「もっとも怖いのは人間の持つ本質的な好奇心だ」と。どんなに危険だと忠告したところで、人は見たがります。本当の脅威とは地下水でも地震でも氷河期でもない、今回の原発や廃棄物といったすべてを作り出したのも好奇心だけれど、その処理を難しくしているのも同じ好奇心なのです。ですからこの映画では核廃棄物がテーマというわけではなく、むしろ「今」という時代は何なのか、それを見つめたものと言えるかもしれません。ですから私は今回福島で起こった災害について「こう処理しろ」と言う気はまったくありません。ただ、処理の方法いかんによっては、これが手のつけようのない惨事に発展してしまうかもしれない。それを防ぐためにも、人々が現実を見つめ、話し合わなければならない時がきているのかもしれないと思います。
津田:「オンカロ」という施設を隠すべきだと運営会社が主張する一方、国は恒久的に伝えるべきだと主張する。この映画では両者の対立が描かれますよね。
マドセン:「隠すべき」というのは、未来の人間や生物に取り扱いマニュアルのない大きな設備を残してしまうことになるからですよね。そう考えると「伝えるべき」と主張する側はある意味、非常に思い上がっているとも言える。ただ「隠すべき」と主張する側は「この建造物が10万年持って何の事故も起きない」という絶対的な自信が裏にあるからでしょう。私は10万年後へのメッセージを残すという可能性に賭けてみるべきだと思います。成功するかどうかはわからないけれど、試みるだけの価値はあると。
津田:オンカロの運営会社と国の対立は、ちょっと日本の状況——東電と国の関係にも似ているな、と思いました。この前、福島のあるゴルフ場が東電を相手取って「福島第一原発の事故によって放射性物質で汚染され、営業に支障が出た」として、除染を求めて裁判を起こしたんですね。このゴルフ場は結局、裁判に負けてしまったんです。東電に言わせれば、「除染は国が行うことになっている、だから我々は補償しない」と。[*2] 国と東電がお互い責任をなすりつけあっているうちに、責任の所在が曖昧になってしまう。これは日本ではよくあるケースです。これを打破するカギは、この映画でも描かれているとおり、話し合いをしていくことなんじゃないかと思うんですよね。
マドセン:原発や原子力関連の企業に接触すると、誰もが必ず自然保護団体のグリーンピースみたいな扱いを受けるんですね。「何をするのだろう」と警戒されるんです。でも「あなたたちのしていることを純粋に知りたい」と率直に言うわけです。私自身は科学者ではないので、科学者をアドバイザーにつけて彼らの言葉を正しく理解する努力をしました。つまり、彼らの言い分が科学的な理屈や根拠に基づいており、思いつきや感情論ではないと理解したうえで、オープンに接するようにした。彼らはどちらかと言うと、テクニカルなことを話したがるんですね。たとえば施設の壁の厚さや素材なんかについて。でも私は哲学的な質問を投げかけたかった。そのために数千ページの研究論文を全部読み、同じ理解の土台に立ったうえで「10万年」というタイムスパンがいったい何を意味するのか、答えざるをえない状況に持っていきました。原発や原子力関連の企業と言っても私企業である以上、利益追求は当然の視点ですし、その中で働いている人は雇われの身です。とはいえ、彼らは原子力の抱える大きな問題を解決するために闘っているのも事実で、希望を持って何かをなしえんとしています。知らないことも当然あります。「廃棄物の責任は出した会社だけではなく、我々皆が負うべきものだから、それをもっとオープンにして一緒に考えたい」。彼らが我々に心を開くきっかけになったのは、そんな発言でした。原発に賛成か反対かにかかわらず、原発による電力を享受している以上、放射性廃棄物は絶対に出てきます。その問題は皆で考えないといけません。原発側をただ敵視し、悪者にして片付ける姿勢ではいけないんです。日本はまさに福島第一原発の事故が起こった今、そのような姿勢を世界に示すいい機会だと思います。
フランスの原子力関連企業でスウェーデンの廃棄物を扱っている女性に、以前話を聞いたことがあります。その時彼女は「福島の状況は特別だ」と言っていたんですね。要は大地震による津波という自然災害に端を発する事故だから、我々には予想しえなかったのだと。しかしこれは、非常に危険な考え方だと私は思います。日本では予測し得ない震度の地震が起こりうる、そんなことはわかっていた。津波だって「tsunami」という呼び方が世界中に広がっているぐらい日本では顕著な現象です。つまり日本が抱えるリスクは数値化不能なほど高いと以前からわかっていたわけです。福島の場合には地震や津波などの不幸な自然災害が何重にも重なったと捉えられていますが、忘れてはいけないのは、人間の犯すヒューマンエラーも予測不能なほど高いということです。たとえば、福島第一原発の事故では防波堤が低すぎて、津波を防げませんでした。もっと高いものが作れたというのに、既にそこであやまちを犯している。事故後の対処も間違っていました。ドイツに至っては、それを受けて脱原発を決めたほどです。「日本ほど高い技術レベルを持っている国で原発事故が起きてしまった、ならば我々はこの技術に信頼を置くことはできない」と言ってね。
津田:映画の後半で監督が運営会社の職員に、放射線廃棄物の再処理について訊きますよね。そうしたらもう明確に「再処理すべきではない。(放射性廃棄物を)無害にするのは現実的に無理だ」という答えが返ってきた。あれは監督が相当勉強されたうえで引き出した言葉ですよね。とてもスリリングで面白いシーンでした。しかし彼らの会社は「放射線廃棄物を再処理せずに貯蔵する」という前提があるからこそ必要とされるという側面があります。あの言葉はそういう前提込みでのポジショントークなのか、それとも本音として「無理だ」と言っているのか、どう思われましたか?
マドセン:フィンランドでは掘削技術が発達しているからこそ、オンカロのような地下施設を作れます。この施設には裏口みたいなものがあって、将来的に放射線廃棄物を取り出せる道を残しているんですね。なぜそうしているのか、本当の理由は私にはわかりません。彼らは原発のゴミを「廃棄物」と呼びながらも一方で「宝物だ」という言い方をしたりします。しかもオンカロの2キロ先には新たな原発が作られている。これを見た人たちは「廃棄物処理の問題を解決したからこそ新たな原発ができたのだ」と言うかもしれません。私はジャーナリストではありませんし、さらなる調査をしないとご質問には答えられません。
津田:あえて単純な質問をさせてください。監督は何千ページもの文献を読んで学習されたと伺いました。知識を得た上で今監督が現時点で原発に賛成か反対かを教えていただけますか。
マドセン:私一人の意見なんて聞いても面白くないでしょう。それよりも、この映画を観た人たちが原発の問題から目をそむけるのではなく、一人でも多く考えてほしいですね。オンカロは永遠に保つとされています。これが果たして我々が今原発を使っていることに対する責任の取り方なのか、永遠とはなんなのか、そういったことを真剣に考え、賢く判断してほしいと思います。
津田:最後の質問です。原発や放射能の問題を語るのは本当に難しい。だからこそ目をそむけ、あえて見ないようにしていた人は日本だけでなく、世界中に一定数いました。この映画にはそういう人たちに「考えないとダメだ」と思わせるパワーがあると思います。また、3.11後の日本では、監督が作品に込めた思いや文脈が、それまでの日本とは異なるリアリティをもって受け取られることになると思います。そのうえで、この映画を観た日本人に、何かメッセージがあればお願いします。
マドセン:まずこの問題について、声を上げて話し合うべきだと思います。そして、誰一人として答えを出すことのできなかった問いへの答えを模索するべきかと。今、欧州の人たちは、東電が日本政府に真実を語らぬままうやむやにしてしまうのか、そして国民がそれを許すのかを注視しています。もし我慢して許してしまったとしたら、まったく理解しがたいミステリーだし、結局、悪い前例を作る結果となってしまうことは明らかだと思いますけどね。私も日本の「恥」の文化はよく知っています。しかし今、それが良くない方向に働き、恥を隠す方向に行っている。今回の原発事故は人類史上最悪の災害の一つで、東電、そして政治の失敗の表れであることは明らかです。それが恥ずかしいからと直視しないで済ませてしまう、見て見ぬふりをするというのでは何の進歩もありません。結局そういうことが堂々巡りするようであれば、信頼というものがまったく存在しない社会であると露呈してしまうのではないか。どうしたらいいかわからなくて当たり前。それを正直に認めてしまうことが実は大事ではないかと思いますね。真実が語られないならば、ジャーナリストはそれを語らせるべきではないでしょうか。今年7月、ノルウェーで青年が銃を乱射するテロが起きましたよね。これがアメリカなら、即「テロとの闘い」になったでしょう。ただノルウェーの反応は違いました。「我々に何が欠けていたのか、デモクラシー的な考えが足りなかったのか、一人ひとりが居場所を見つけられるような社会を構築できていなかったのではないか、もっと包容力のある社会にできないのか」という方向に行ったのです。私はその結論に心打たれるものがありました。日本がもし今の方向性のまま行ってしまえば、こういう部分が欠如することになってしまうのではないでしょうか。
津田:メディアに携わる人間として、大変身につまされる話です……。今日は貴重なお話をありがとうございました。
▼マイケル・マドセン
1971年生まれ。映画監督、コンセプチュアル・アーティスト。ストリンドベリ の『ダマスカスへ』をベースに、都市と景観を上空から撮影した映像作品『To Damascus』(2005)のほか、何本かのドキュメンタリー作品を監督。また、コペンハーゲンのタウンホール広場の地下にある面積900平方メートルのサウンド・ディフージョン・システムを備えたギャラリー『Sound/Gallery』の創始者および芸術監督を務める(1996–2001)。ニューミュージック&サウンドアート・フェスティバル「SPOR 2007」のデザインやデンマークのオーデンセの音楽図書館のコンセプトを考案。また、ゲストスピーカーとして、デンマーク王立芸術学校、デンマーク映画学校、デンマークデザイン学校で講演している。著書に『100,000年後の安全』(かんき出版)。